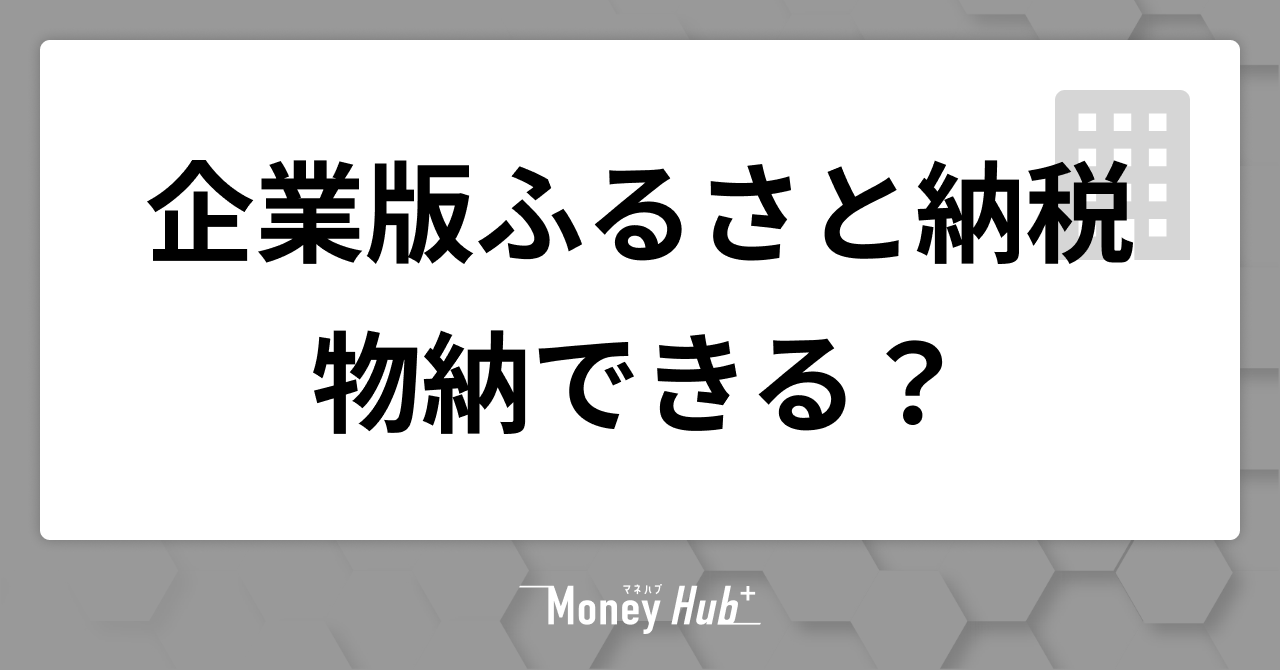
この記事のポイント
- 企業版ふるさと納税では、地方自治体が物品の受け入れを公式に表明している事業であれば、自社製品やサービスなどによる「物納」も可能
- 物納の主なメリットは、現金の支出を抑えて社会貢献できることと、規格外品や余剰在庫などを有効活用できる点だ
- ただし、物納は対象となる事業がまだ少ないことや、寄附する物品の客観的な時価を算定する手間がかかるというデメリットがある
「企業版ふるさと納税、うちの会社もやってみたいけど、まとまった現金の支出はちょっと…」
「自社の製品で社会貢献できるなら、ぜひやりたい!」
企業の経営者や担当者様の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
「企業版ふるさと納税って、現金の寄附だけでしょ?」と思っていませんか?実は、一定の条件を満たせば、自社製品やサービスなどを寄附する「物納」も可能です。
この記事では、企業版ふるさと納税で「物納」を行うための具体的な方法、メリット、そして注意点を、誰にでも分かりやすく解説していきます。
「企業版ふるさと納税を始めたい!」そんな方へ

制度の概要やメリット、実際の活用事例などをまとめた概要資料をご用意しました。
寄附による合計軽減額(控除額)を大まかに把握できるシミュレーション資料も含めております。
ぜひご活用ください!
INDEX
【結論】「物納」ができるのはどんな時?
さっそく結論から。企業版ふるさと納税で物納ができるかどうかは、「地方自治体が、物納を受け入れる事業を行っているかどうか」にかかっています。
条件は「自治体が物納を受け入れる事業を行っている」こと
すべての事業で物納が可能なわけではありません。企業版ふるさと納税の対象事業の中で、地方自治体が「このプロジェクトでは、企業からの物品提供を歓迎します!」と公式に表明している場合に限り、物納による寄附が選択肢となります。
どうやって探す?物納可能な事業の見つけ方
では、どうすれば物納OKな事業を見つけられるのでしょうか。主な探し方は3つです。
- 探し方1:自治体のウェブサイトで直接確認する
応援したい特定の自治体がある場合、その自治体の企業版ふるさと納税に関するページを直接チェックしてみましょう。「物品による寄附を受け付けます」といった記載が見つかることがあります。 - 探し方2:ポータルサイトでキーワード検索してみる
内閣府の「企業版ふるさと納税ポータルサイト」などで事業を検索する際に、「物品提供」「物納」といったキーワードで絞り込んでみるのも一つの手です。 - 探し方3:専門の支援サービスに相談する
「探す時間がない」「自社製品を活かせる寄附先がわからない」という場合は、プロに相談するのが一番の近道です。専門のマッチングサービスなら、全国の膨大な事業の中から、貴社に最適な物納先を提案してくれます。
メリット・デメリットで比較!「物納」と「現金寄附」どっちを選ぶ?
自社に合うのはどちらのスタイルか、それぞれのメリット・デメリットを比べて考えてみましょう。
| 物納による寄附 | 現金による寄附 | |
|---|---|---|
| メリット | ・キャッシュアウトを抑えられる ・在庫を有効活用できる | ・寄附先を自由に選べる ・手続きがシンプル |
| デメリット | ・対象事業が限られる ・寄附額の評価(時価)が必要 | ・一時的に現金が流出する |
「物納」を選ぶメリット・デメリット
【メリット】
- キャッシュアウトを抑えられる: なんと言っても最大のメリットは、現金の支出をせずに税制優遇を受けながら社会貢献ができる点です。
- 在庫を有効活用できる: 規格外品や余剰在庫など、倉庫に眠っている資産を価値あるものとして有効活用できます。
【デメリット】
- 対象事業が限られる: 物納を受け入れている事業自体がまだ少ないため、寄附先を探すのに手間がかかる場合があります。
- 寄附額の評価が必要: 税額控除の基となる寄附額を算出するために、寄附する物品の客観的な価値(時価)を算定する手間がかかります。
「現金寄附」を選ぶメリット・デメリット
【メリット】
- 寄附先を自由に選べる: 全国のほぼ全ての対象事業の中から、自社の理念や事業に合ったプロジェクトを自由に選んで応援できます。
- 手続きがシンプル: 寄附額が明確なため、時価評価などの手間がなく、手続きがスムーズに進みます。
【デメリット】
- 現金が流出する: 一時的ではありますが、会社のキャッシュフローに影響が出ます。(ただし、最大9割の税優遇があるため実質負担は1割程度です)
あわせて読みたい
【3ステップ】物納で寄附する時の大まかな流れ
実際に物納で寄附を進める際の、基本的な流れを3ステップでご紹介します。
STEP1:物納可能な事業を探し、自治体に相談する
まずは、受け入れてくれる自治体・事業を見つけることが全てのスタートです。自治体の担当窓口に連絡を取り、寄附したい物品の内容や希望する寄附額を伝え、受け入れが可能かどうかを具体的に相談しましょう。
STEP2:寄附する物品の「時価」を確認し、寄附申出書を提出
自治体との間で合意が取れたら、寄附する物品の金額を確定させます。この金額は、誰が見ても納得できる客観的な市場価格、すなわち「時価」である必要があります。金額が確定したら、自治体の指定する寄附申出書を提出します。
STEP3:物品を納付し、受領証を受け取って税務申告
自治体の指示に従って、指定された場所や方法で物品を納付します。納付が完了すると、後日、自治体から寄附額が記載された「受領証」が送られてきます。この受領証は税務申告で必要になるので、大切に保管し、法人税の申告時に添付してください。
まとめ:自社に合った方法で、賢く社会貢献を始めよう!
今回は、企業版ふるさと納税の「物納」について、その可能性や具体的な進め方をご紹介しました。
物納はキャッシュアウトを抑えられる魅力的な方法ですが、対象事業が限られるといった側面もあります。一方で、現金での寄附は、寄附先を自由に選べ、最大9割の税優遇を受けられるという大きなメリットがあります。
それぞれの特徴を理解し、ぜひ貴社に最適な方法で、賢い社会貢献の一歩を踏み出してみてください。
「うちの会社は物納できる?」「良い寄附先は?」…そのお悩み、プロに相談しませんか?
「自社製品を活かせる物納先を、効率よく見つけたい」
「自治体との調整や、時価の算定など、手続きがなんだか大変そう…」
そんなお悩みや不安は、私たち「企業版ふるさと納税ナビ」にぜひお任せください!
全国の自治体との豊富なネットワークを活かし、貴社の製品やサービスを本当に必要としている物納先とのマッチングを強力にサポート。もちろん、面倒な手続きや自治体との調整も、専門スタッフが最後まで伴走し、貴社の負担を最小限に抑えます。
まずはお気軽に、無料相談の窓口からお問い合わせください。
「企業版ふるさと納税を始めたい!」そんな方へ

制度の概要やメリット、実際の活用事例などをまとめた概要資料をご用意しました。
寄附による合計軽減額(控除額)を大まかに把握できるシミュレーション資料も含めております。
ぜひご活用ください!
このコラムの執筆者

MONEY HUB PLUS 編集部
株式会社Fan
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

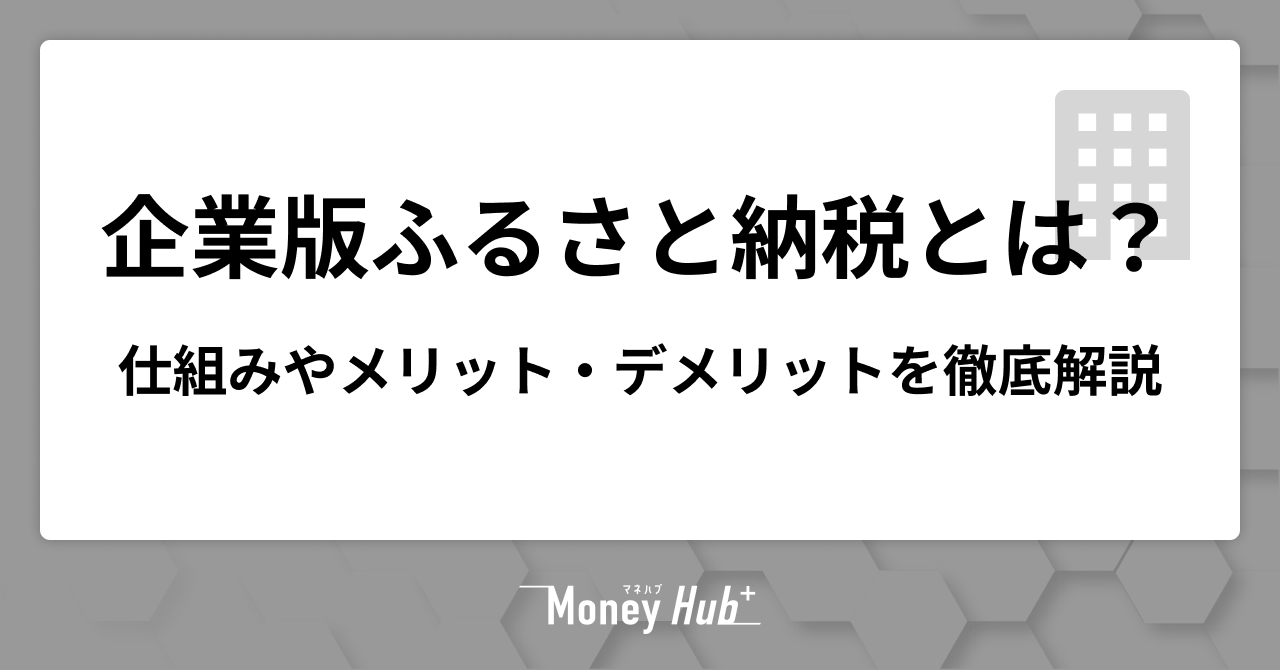































































未来につながる投資情報メディア「Money Hub Plus(マネハブ)」の編集部です。
みなさまの資産形成に役立つ情報を日々発信しております。