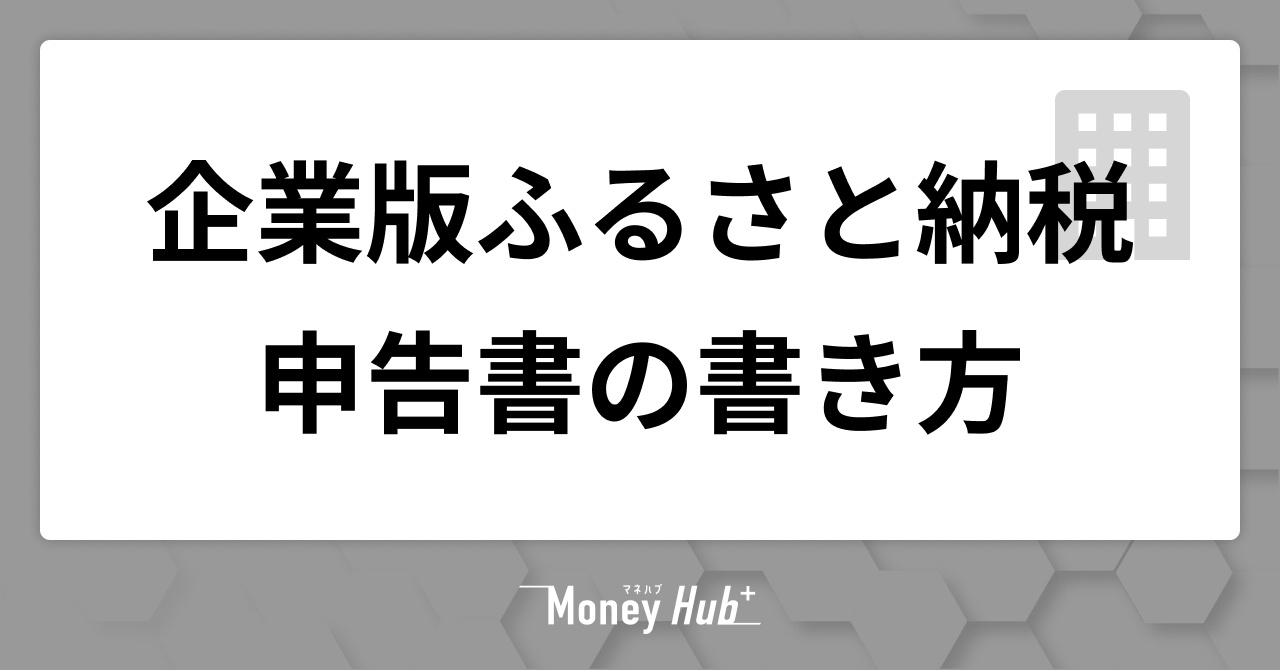
この記事のポイント
- 企業版ふるさと納税の最大のメリットは最大約9割の税軽減効果
- 手続きは「寄付→領収書受領→申告」の3ステップで完了
- 税額控除の上限を把握し、節税効果を最大化することが成功の鍵
「企業版ふるさと納税で社会貢献と節税をしたいけれど、申告手続きが複雑そうで不安…」
「法人税の申告書の書き方がわからず、なかなか一歩を踏み出せない」
企業の経営者様や経理ご担当者様から、このようなお悩みをよくお伺いします。
企業版ふるさと納税(正式名称:地方創生応援税制)は、企業が応援したい地方公共団体の事業へ寄附をすることで、最大で寄附額の約9割に相当する税の軽減効果が受けられる、非常に魅力的な制度です。
しかし、そのメリットを最大限に享受するためには、法人税の申告を正確に行う必要があります。
ご安心ください。この記事を最後までお読みいただければ、企業版ふるさと納税の申告書の書き方から、一連の手続きの流れまでを具体的に理解できます。煩雑に思える申告業務の不安を解消し、自信を持って制度をご活用いただくための一助となれば幸いです。
「企業版ふるさと納税を始めたい!」そんな方へ

制度の概要やメリット、実際の活用事例などをまとめた概要資料をご用意しました。
寄附による合計軽減額(控除額)を大まかに把握できるシミュレーション資料も含めております。
ぜひご活用ください!
INDEX
【前提】企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の仕組みをおさらい
まず、なぜこの制度がこれほど注目されているのか、税軽減の仕組みを簡単におさらいしましょう。
企業版ふるさと納税では、寄附を行った際に「損金算入」と「税額控除」という2段階の税制優遇が受けられます。この税制優遇を受けることのできる対象法人は、外国法人を含め、青色申告書を提出する法人となります。
- 損金算入による軽減効果(約3割)
寄附額の全額を損金として算入できるため、法人関係税(法人税・法人住民税・法人事業税)が軽減されます。これは通常の寄附金と同様の措置です。 - 税額控除による軽減効果(最大6割)
上記①に加え、寄附額の最大6割が法人関係税の税額から直接控除されます。これにより、企業の実質的な負担を寄附額の約1割にまで圧縮することが可能です。
この2つの措置を合わせることで、最大で寄附額の約9割という大きな税負担軽減効果が生まれるのです。このメリットを確実に受けるために、次の章で解説する正しい手続きと申告が不可欠となります。
あわせて読みたい
申告前に確認!企業版ふるさと納税の手続き全体の流れ
申告書の作成は、手続き全体の最終ステップです。まずは寄附から申告までの流れを把握しておきましょう。
- STEP1:寄附の申し込みと実施
内閣府の「企業版ふるさと納税ポータルサイト」などで、応援したい地方公共団体の事業を探し、寄附を申し込みます。 - STEP2:地方公共団体から「領収書(寄附金受領証)」を受け取る
寄附金の入金確認後、寄附先の地方公共団体から「領収書(寄附金受領証)」が発行されます。これは後の税務申告で必須の書類となるため、大切に保管してください。 - STEP3:税の申告手続きを行う
事業年度終了後、法人税の確定申告の際に、所定の申告書を作成し、領収書を添付して税務署等に提出します。
【本題】企業版ふるさと納税の申告書の書き方を2ステップで徹底解説
ここからが本題です。税務申告を2つのステップに分けて、具体的に解説していきます。
ステップ1:必要書類を準備する
まず、申告にあたって以下の書類を手元に揃えましょう。
| 必要書類 | 概要 | 入手先 |
|---|---|---|
| 法人税申告書 | 通常の法人税申告で用いる各種別表 | 国税庁HP、税務ソフト 等 |
| 適用額明細書 | 地方創生応援税制の税額控除について記載する書類 | 国税庁HP、企業の所在地を管轄する都道府県税事務所や各市町村の市民税課のHP等 |
| 寄附金の領収書 | 寄附を証明する書類 | 寄附先の地方公共団体 |
特に「適用額明細書」は、この制度特有の書類ですので、国税庁のウェブサイト等から最新の様式をダウンロードしてください。
出典:法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)|国税庁 (※令和7年8月14日時点)
ステップ2:税額控除額を計算し、申告書に記入する
書類の準備が整ったら、税額控除額を計算し、申告書に記入していきます。少し複雑に感じますが、順番に見ていけば大丈夫です。
✅ まず、税額控除額を計算する
税額控除は、①法人事業税、②法人住民税、③法人税の3つの税金から行われます。ここでは、仮に100万円を寄附した場合を例に、計算の順番とポイントを解説します。
①【法人事業税(地方税)】からの控除額
100万円(寄附額) × 20% = 20万円
ただし、その年度の法人事業税額の20%が上限です。
②【法人住民税(地方税)】からの控除額
100万円(寄附額) × 40%(※) = 40万円
(※内訳:道府県分5.7%、市町村分34.3%)
ただし、その年度の法人住民税法人税割額の20%が上限です。
③【法人税】からの控除額
(100万円 × 40%) – (②法人住民税の実際の控除額)
ただし、その年度の法人税額の5%が上限です。
【ここが重要!】法人住民税と法人税の関係
「寄附額の40%」という大きな控除枠を、まず②法人住民税で使います。もし、法人住民税の納税額が少なく、上限に達して40万円分を使いきれなかった場合、その使いきれなかった残りの枠を③法人税から控除できる、という仕組みです。
(例)上記の例で法人住民税の上限額が30万円だった場合
- ②法人住民税からの控除は30万円
- 使いきれなかった枠は 40万円 – 30万円 = 10万円
- この10万円を③法人税から控除します(法人税額の5%という上限内で)
このように、各税金の上限額を確認しながら、順番に計算していくことが大切です。
✅ 次に、法人税申告書に記入する
計算が終わったら、申告書に記入します。企業版ふるさと納税の申告は、国税(法人税)と地方税(法人事業税・法人住民税)でそれぞれ手続きが必要です。
①国税(法人税)の申告:損金算入のための手続き
まず、寄附金を損金として算入するための手続きです。この別表では、支出した寄附金の額や損金算入額を記入します。企業版ふるさと納税による寄附金は、全額が損金算入の対象となります。
「別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書」に、寄附金の全額を記入します。これにより、寄附額が課税所得から控除され、法人税等の負担が軽減されます。
出典:令和5年4月から令和6年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和5年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 (※令和7年8月14日時点)
別表十四(二) 「寄附金の損金算入に関する明細書」■申告書作成上の留意点|国税庁 (※令和7年8月14日時点)
【記入のポイント】
- 「指定寄附金等の額」の欄に、今回の寄附金額を記入。(※)
- これにより、寄附額が課税所得から控除され、法人税等の負担が軽減される。
※「支出した寄附金の額」には、仮払寄附金の額は含まれますが、未払寄附金の額は含まれません。
②国税(法人税)の特別控除を受けるための手続き
まず、特定寄附金の金額を記入します。次に、下記の手順で記入を進めていきます。
税額控除限度額:下記の式で「特定寄附金基準額」と「差引税額控除基準額残額」を計算し、そのうち小さい方の金額が「税額控除限度額」となります。
特定寄附金基準額:寄附金の額 × 10%
差引税額控除基準額残額:(寄附金の額 × 40%) − 実際に控除した法人住民税の金額
当期税額控除可能額:下記の式で「当期税額基準額」を計算し、「税額控除限度額」と比較します。そのうち小さい方の金額が、納めるべき法人税額から直接差し引かれます。
当期税額控除可能額の計算:当期税額基準額:その年度の法人税額 × 5%
「別表六(二十四)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に、法人税から控除する金額を記入します。
出典:令和5年4月から令和6年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和5年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁 (※令和7年8月14日時点)
別表六(二十四)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書■中小企業向け租税特別措置等の適用を受ける場合の判定について|国税庁 (※令和7年8月14日時点)
③地方税(法人事業税・法人住民税)の税額控除を受けるための手続き
以下の書類を記入し、企業の所在地を管轄する都道府県税事務所や各市町村の市民税課へ提出します。
- 法人事業税:(第七号の三様式)特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
- 法人住民税:(第二十号の五様式)特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
各様式は自治体のホームページで取得が可能です。また、寄附先の自治体から発行された受領書の写しも必要となります。紛失しないよう管理しましょう。
参考:特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式)|茨城県 (※令和7年8月14日時点)
【法人市民税】特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)|金沢市 (※令和7年8月14日時点)
企業版ふるさと納税の申告に関するQ&A
Q1. 申告書の提出期限はいつですか?
A1. 通常の法人税の申告・納付期限と同様で、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば、決算日が3月31日の企業の場合、申告期限は5月31日です。この期限に間に合うよう、寄附金の納付を完了させ、自治体から発行される領収書(寄附金受領証)を準備しておく必要があります。
■利益が少ない場合の注意点
企業版ふるさと納税は、実際に納めるべき法人税等の金額から控除される制度です。そのため、そもそも利益が少なく、納める税金がない場合は、控除のメリットを十分に受けられない可能性があります。
つまり、支出額に対して必ず90%の軽減効果があるわけではありません。税制上のメリットを最大限享受するには、寄附金額と比較して十分な所得がなければいけません。税務申告の詳細については、複雑な点も多いため、税理士や税務署に確認することをおすすめします。
Q2. 申告書を提出するのはどこですか?
A2. 国税(法人税)の申告については納税地を所轄する税務署です。e-Taxによる電子申告も可能です。
また、地方税(法人事業税・法人住民税)の申告については企業の所在地を管轄する都道府県税事務所や各市町村の市民税課へ提出します。
Q3. もし申告内容を間違えたらどうなりますか?
A3. 控除額の計算ミスや添付書類の不備があった場合、税務署から是正を求められたり、本来受けられるはずの税制優遇が受けられなくなったりする可能性があります。
誤りに気づいた場合は、速やかに修正申告等の手続きを行いましょう。
「手続きが複雑…」と感じたら専門家への相談が近道です
ここまで申告書の書き方や手続きの流れを解説してきましたが、 「やはり自社だけで正確に申告できるか不安…」 「計算や書類作成に時間を取られ、本業に集中できない…」 と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
特に、初めてこの制度を利用する場合や、経理担当者様のリソースが限られている場合には、専門的な支援サービスを活用することが、結果的に最も確実で効率的な選択肢となります。
私たちが提供する「企業版ふるさと納税ナビ」は、制度を熟知した専門家が、貴社に最適な寄附先の選定から、節税効果のシミュレーション、煩雑な申告手続きのサポートまでをワンストップでご支援するサービスです。
- 専門家による丁寧なヒアリングで、貴社の課題や想いに合った寄附先をご提案
- 税額控除シミュレーションで、節税効果の最大化を実現
- 申告書類作成のサポートで、経理担当者様の負担を大幅に削減
申告手続きの不安を解消し、安心して社会貢献活動に取り組みたいとお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、企業版ふるさと納税の申告書の書き方を中心に、手続きの全体像を解説しました。
- 最大のメリットは最大約9割の税軽減効果
- 手続きは「寄附→領収書受領→申告」の3ステップで完了
- 税額控除の上限を把握し、節税効果を最大化することが成功の鍵
この制度を正しく活用することは、企業の税負担を軽減するだけでなく、応援したい地域の活性化に直接貢献できる、意義深い活動です。
本記事が、貴社の企業版ふるさと納税への取り組みの一助となれば幸いです。もし手続きにご不安があれば、いつでも「企業版ふるさと納税ナビ」にご相談ください。
「企業版ふるさと納税を始めたい!」そんな方へ

制度の概要やメリット、実際の活用事例などをまとめた概要資料をご用意しました。
寄附による合計軽減額(控除額)を大まかに把握できるシミュレーション資料も含めております。
ぜひご活用ください!
このコラムの執筆者

MONEY HUB PLUS 編集部
株式会社Fan
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

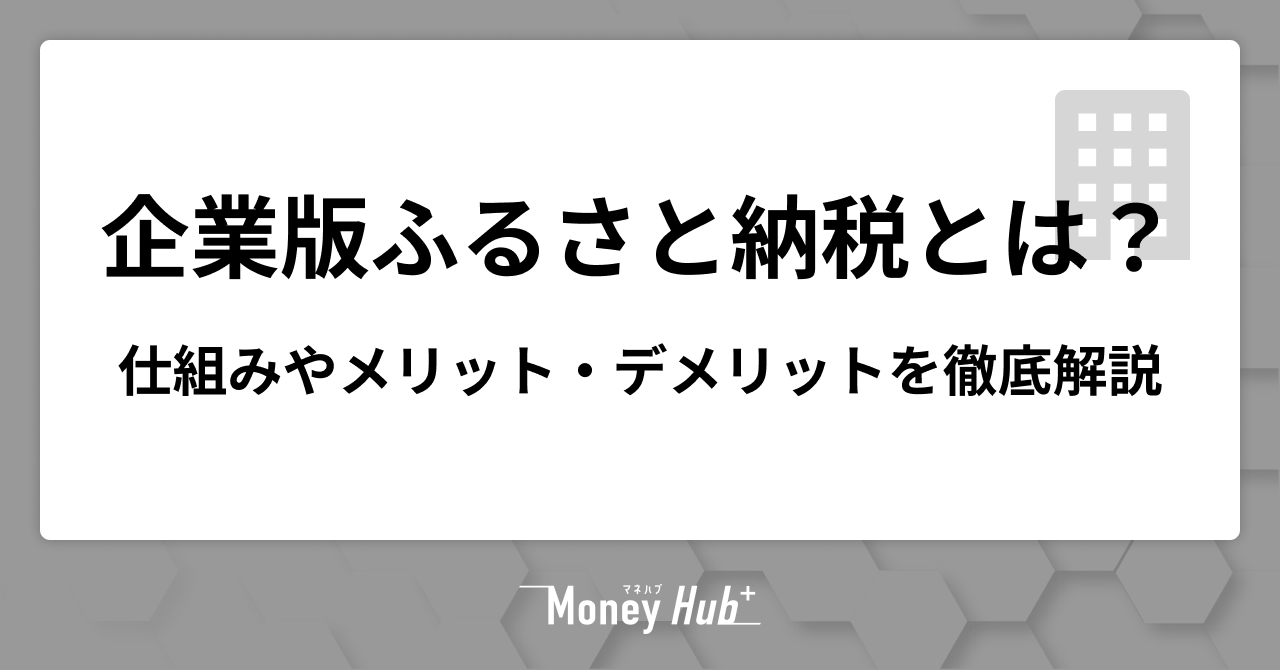
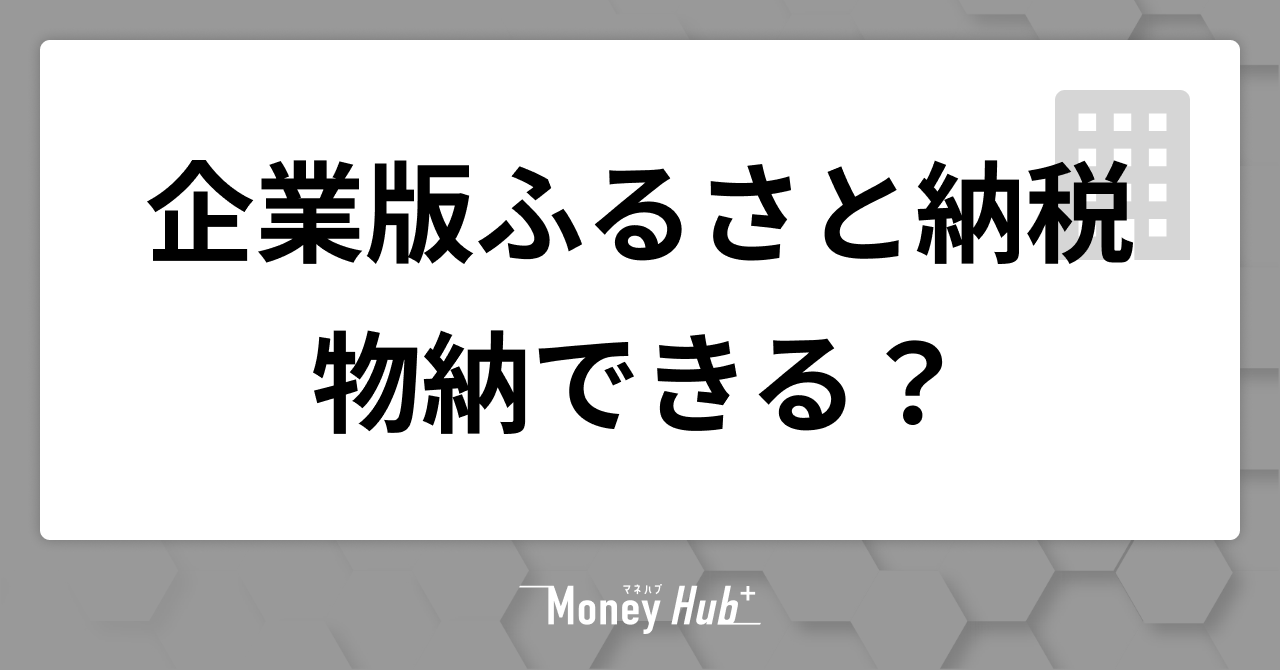































































未来につながる投資情報メディア「Money Hub Plus(マネハブ)」の編集部です。
みなさまの資産形成に役立つ情報を日々発信しております。