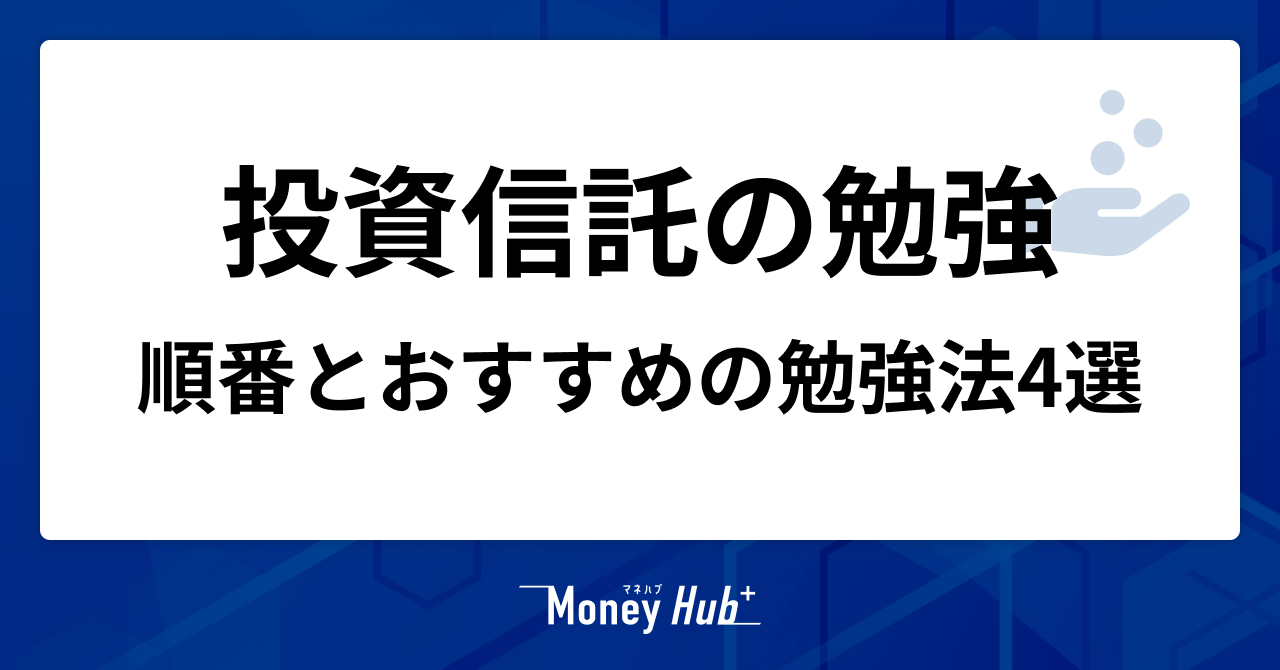
この記事のポイント
- 投資信託の学習は、「全体像の把握 → 自分に合った学習 → 少額での実践」という3ステップで進めることが推奨される
- 知識を深めるには、本/Webサイト/セミナーといった複数の方法を組み合わせるのが効果的である
- 独学に不安を感じる場合、特定の金融機関に属さない中立的なアドバイザー(IFA)に相談することも有効な選択肢である
「将来のために資産形成を始めたいけど、何から手をつければ…」
「投資信託がいいって聞くけど、勉強方法がわからなくて一歩が踏み出せない」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
将来のお金に対する漠然とした不安から、投資信託に興味を持つ方は年々増えています。しかし、専門用語の多さや情報の複雑さから、投資信託の勉強を始める前につまずいてしまう方が非常に多いのも事実です。
この記事では、IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)として多くのお客様のお悩みに向き合ってきた経験をもとに、投資知識ゼロの初心者の方におすすめな投資信託の勉強法を、具体的なロードマップに沿って分かりやすく解説します。
この記事を読めば、きっとあなたが今何をすべきかが明確になります。ぜひ最後までご覧ください。
「これから資産運用を始めたい!」そんな方へ

資産運用の基本や運用のコツ、活用したい制度や実践方法など、資産運用の基礎をまるごと学べるハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
INDEX
【3ステップ】失敗しないための投資信託の勉強ロードマップ
「よし、勉強するぞ!」と意気込んでも、やみくもに始めては非効率です。ここでは、初心者が最短で投資信託を理解するための勉強方法を次の3つのステップに分けてご紹介します。
- STEP1:まずは基本のキ!投資信託の全体像を掴む
- STEP2:投資信託のおすすめ勉強法4選!自分に合った方法で知識を深めよう
- STEP3:月々1,000円からでもOK!少額で実践してみる
STEP1:まずは基本のキ!投資信託の全体像を掴む
最初から細かい部分を詰め込む必要はありません。まずは森全体を眺めるように、以下の5つのポイントを押さえましょう。
最低限押さえたい5つの基礎知識
1.投資信託の仕組み
多くの投資家から集めたお金を、運用のプロ(ファンドマネージャー)が株式や債券などに投資・運用する金融商品。一つの商品で様々な資産に分散投資できるのが最大のメリット。
2.主な投資対象
自分が買う投資信託が、何に投資しているのかを知りましょう。(例:国内株式、先進国株式、新興国株式、債券、不動産(REIT)など)
3.ファンドの種類
- インデックスファンド:市場平均(例:日経平均株価)と同じような値動きを目指す。低コストで初心者向け。
- アクティブファンド:市場平均を上回るリターンを目指す。コストは高め。
4.手数料(コスト)
投資信託には「購入時手数料」「信託報酬(保有中にかかる費用)」「信託財産留保額(解約時費用)」などのコストがかかります。特に信託報酬は長期的なリターンに大きく影響するため要チェックです。
5.NISA制度の概要
投資で得た利益が非課税になる制度。まずはこの制度を活用することを検討してみましょう。
あわせて読みたい
「NISAを使って資産運用を始めたい!」そんな方へ
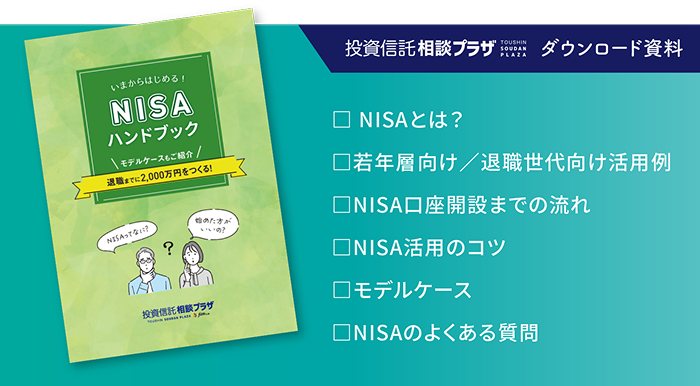
NISA(少額投資非課税制度)のしくみや活用のコツ、実際の活用例などをまとめたハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
STEP2:投資信託のおすすめ勉強法4選!自分に合った方法で知識を深めよう
基礎知識の全体像が掴めたら、次に紹介する具体的な勉強法の中から、ご自身のライフスタイルや好みに合ったものを選んで知識を深めていきましょう。
ここでは、ステップ2を具体的に進めるための4つの勉強法をご紹介します。それぞれにメリット・デメリットがあるので、複数を組み合わせるのがおすすめです。
勉強法1:本で体系的に学ぶ
- メリット:専門家によって情報が整理されており、順序立てて体系的に学べる。信頼性が高い。
- デメリット:発行時期によっては情報が古い場合がある。読むのに時間がかかる。
まずは、投資信託に関するベストセラー本を2〜3冊読んでみるのがおすすめです。多くの人に読まれている本は、初心者にも理解しやすいように工夫されていることが多いからです。
ただし、書かれている内容をすべて鵜呑みにするのは禁物です。著者によって考え方や推奨する手法は異なりますし、時代背景に合わせて効果的な投資法も変わります。複数の本を読み比べることで、多角的な視点を養い、自分なりの投資の軸を見つけることが大切です。
勉強法2:Webサイトで最新情報をチェックする
- メリット:最新の情報を無料で手に入れられる。スマホで手軽に確認できる。
- デメリット:情報が玉石混交で、信頼性の見極めが必要。情報が断片的になりがち。
✅️ おすすめのWebサイト3選
- 金融庁「NISA特設ウェブサイト」:NISA制度に関する公式情報がまとめられています。まずはここから確認しましょう。
参照:金融庁「NISA特設ウェブサイト」 - 投資信託協会:投資信託に関する様々な統計データや、基礎知識を学べるコンテンツが充実しています
参照:投資信託協会 - 各証券会社のコラムやオウンドメディア:SBI証券の「投資情報メディア」や楽天証券の「トウシル」など、口座開設者でなくても読める質の高い記事が多くあります。
勉強法3:証券会社の無料セミナーに参加する
- メリット:無料で専門家の話を直接聞ける。質問できる機会がある。
勉強法4:中立的なアドバイザー(IFA)のセミナーや相談会で客観的に学ぶ
「豊富なラインナップから商品を紹介して欲しい」「中立的な意見を聞きたい」 という方におすすめなのが、IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)が開催するセミナーや相談会です。
✅️ IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)とは?
特定の銀行や証券会社に所属せず、公正・中立の立場で顧客の資産運用に関するアドバイスを行う専門家のことです。中立的な立場から、複数の金融機関の商品を比較検討し、顧客にとってより良い選択肢の提案ができる可能性があります。
また、一般的に担当者の転勤がないため、長期的な視点で顧客の資産運用のサポートを期待できます。
私たち「投資信託相談プラザ」も、このIFAに該当します。また、弊社のIFAによるご相談は、お客様にご納得いただけるまで、無料で何度でもご利用いただけます。特定の金融商品を売ることが目的ではなく、お客様一人ひとりの状況に合わせた資産形成プランを、中立的な立場からご提案することを使命としています。
独学だけで資産運用を始めるのは不安な方もいらっしゃるでしょう。
投資信託相談プラザにご相談に来られる方の多くが、同じ不安を抱えています。「自分の勉強法は合っているのか」「どの商品を選べばいいのか最終的な判断ができない」といった悩みは尽きないものです。
独学は素晴らしい第一歩ですが、客観的な視点を持つIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)に相談することで、時間と労力を大幅に節約しながら、資産運用をスタートできます。
あわせて読みたい
「資産運用を体系的に学びたい!」そんな方へ

私たち「投資信託相談プラザ」は、毎月全国各地・オンラインにて資産運用セミナーを開催しています。(参加費無料)
参加者数は延べ70,000人超(※)。ぜひお気軽にご参加ください!
※2015年12月~2025年7月末までの実績
\ SBI証券 共催・楽天証券 協賛 /
STEP3:月々1,000円からでもOK!少額で実践してみる
知識をインプットするだけでなく、実際に少額からでも始めてみることが何よりの勉強になります。
- 値動きを実際に体験することで、経済ニュースへの感度が高まる
- 「なぜ上がったのか?」「なぜ下がったのか?」を調べる習慣がつく
- 自分のリスク許容度(どれくらいの値下がりまで精神的に耐えられるか)がわかる
ネット証券なら月々1,000円や、100円から積立設定が可能です。「習うより慣れよ」の精神で、まずは家計に無理のない範囲で一歩を踏み出してみましょう。
あわせて読みたい
まとめ:投資信託の勉強は未来への自己投資。でも、一人で悩まないで
今回は、知識ゼロから始める投資信託の勉強法について、具体的なロードマップとおすすめの方法を解説しました。
- 「全体像の把握 → 自分に合った学習 → 少額実践」の3ステップで進める
- 知識の習得には、本、Web、動画、セミナーなど複数の方法を組み合わせるのが効果的
- 独学に不安を感じたら、中立的なアドバイザー(IFA)に相談するのも有効な選択肢
投資信託の勉強は、豊かな未来を築くための「自己投資」です。しかし、大切なお金のことだからこそ、一人で全ての不安を抱え込む必要はありません。
もしあなたが、「効率よく体系的に学びたい」「自分に合ったプランを客観的な立場でアドバイスしてほしい」と感じているなら、一度私たちの資産運用セミナーに参加してみませんか?
「投資信託相談プラザ」では、無理な勧誘は一切行いません。まずは投資の基本を学び、疑問点を解消する場として、お気軽にご活用ください。あなたの資産形成の第一歩を、私たちが全力でサポートします。
このコラムの執筆者

道谷 昌弘
株式会社Fan IFA
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。



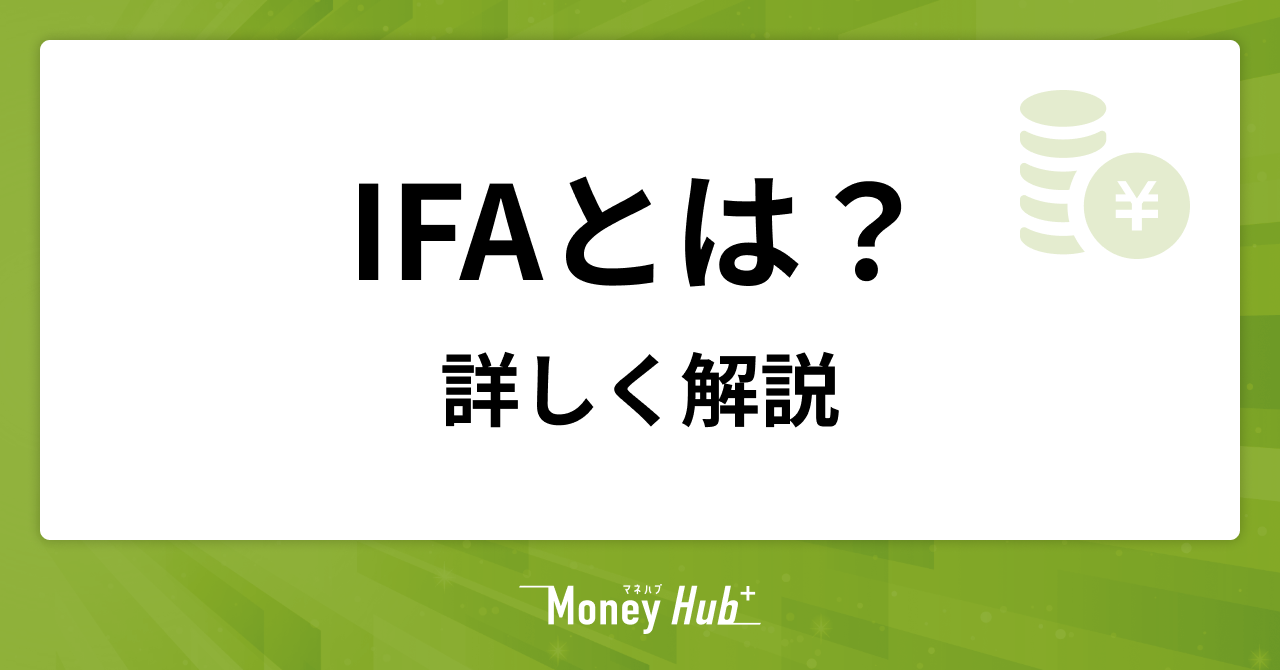































































AFP(日本FP協会認定) 大学卒業後、大手証券会社に入社。国内営業部門にて法人・個人の資産運用アドバイスを行う。8年間勤めたのち退社し、より中立的なアドバイスができるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。現在は富山を拠点に、全国各地のお客様に幅広くコンサルティングを行いながら、お客様にとって本当に良い商品提案を日々追求している。