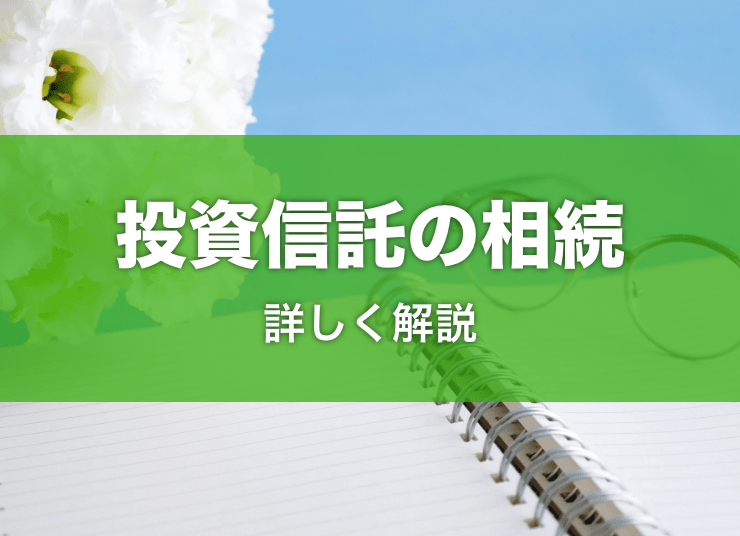
投資信託の買付を検討中の方も、既に投資信託に投資をしている方も、気になるのは相続発生時に資産がどう評価されるのか、またどのような流れで相続されるのかということではないでしょうか。
この記事では、投資信託の相続手続きの流れや相続税評価方法などの基礎知識に加えて、相続対策として投資信託を取り入れるメリットについて解説していきます。ぜひ参考にしてください。
INDEX
投資信託とは

投資信託は、投資家から集めたお金を資産運用会社(ファンドなど)に預け、運用のプロであるファンドマネージャーが株式や債券などで運用します。
得られた収益はそれぞれの投資額に応じて分配される仕組みです。少額から始められることや、投資のプロに任せることができるため、投資初心者でも気軽に資産運用ができるのがメリットです。
しかし、元本保証がないことや、各種手数料が必要というデメリットも存在します。
投資信託の相続税評価方法

投資信託の相続税評価方法についてみていきましょう。
一般的な投資信託
次の算式により計算した金額によって評価します。
課税時期1口当たりの基準価額×口数-課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額-信託財産留保額および解約手数料(消費税額に相当する額を含む)
基準価額は、投資信託の値段のことです。口数とは、保有している投資信託の数量です。
つまり相続税評価額を算出するには、まず投資信託自体の評価額を算出し、そこから源泉徴収税額を差し引き、さらに信託財産留保額や解約手数料を差し引きます。
源泉徴収税額は、相続発生日時点の利益に対して課税されます。マイナス運用の場合は、発生しない場合もあります。
日々決算型の投資信託
中期国債ファンドやMMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の場合、次の算式により計算した金額によって評価します。
1口当たりの基準価額×口数+再投資されていない未収分配金(A)-Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額-信託財産留保額および解約手数料(消費税額に相当する額を含む)
(注)上記算式中の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、特別徴収されるべき道府県民税相当額および復興特別所得税の額に相当する金額を含みます。
ETF・REITの場合
ETF、REITなどの上場投資信託については、上場株式と同様に4つの方法から最も低い金額で評価します。
亡くなった日(相続発生日)を、2024年7月1日と仮定します。
- 相続発生日の最終価格:2024年7月1日の終値
- 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額:2024年7月の毎日の終値の平均
- 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額:2024年6月の毎日の終値の平均
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額:2024年5月の毎日の終値の平均
この4つの中で最も低い金額が相続税評価額となります。
出典:国税庁 上場株式の評価
投資信託の相続手続きの流れ

ここからは、投資信託をお持ちの方が亡くなられた場合の、一般的な相続手続きの流れを解説していきます。
1.金融機関に被相続人の死亡を連絡
まず、被相続人が口座を開設していた金融機関へ、亡くなった旨を伝えます。必要な書類や手続きの方法についてはこのタイミングで金融機関の担当者から説明があります。
2.投資信託の遺産分割方法を確定する
遺言書がある場合
有効な遺言書がある場合、遺言の内容に従います。
遺言書がない・もしくは遺産分割の方法が指定されていない場合
有効な遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
3.金融機関で手続きをすすめる
相続人全員の同意が取れれば、相続手続きを進めることができます。金融機関が求める書類を提出し、手続きをします。
4.投資信託の移管が完了
被相続人の口座から、相続人の口座へ投資信託を移管します。そのまま保有を継続するか、売却するかは遺産分割協議で定めた内容に従います。
相続人が被相続人の口座に受け入れられていた投資信託を相続するためには、原則として被相続人の口座と同じ金融機関に相続人名義の口座を開設する必要があります。(既に口座がある場合は改めて開設する必要はありません。)
NISA口座の開設者が亡くなった場合

NISA口座で保有している投資信託を相続する方法とは
NISA口座を使って投資信託を保有している被相続人が亡くなったとします。
まず、NISA口座での運用の有無に関係なく、投資信託をそのまま売却したり、運用益を受け取ることはできません。運用を続けるもしくは売却して清算したい場合、先述した相続手続きが必要です。
さらに、NISA口座が開設されている金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出しなくてはいけません。
被相続人の口座に受け入れられていた投資信託が遺産分割される場合は、相続人の特定口座や一般口座に移管されます。
この場合、相続人がNISA口座を持っていても、その口座へ移管することはできません。NISA口座の非課税措置は、被相続人の死亡によって終了するからです。
NISA口座の開設者が亡くなったあとの非課税措置の適用範囲
NISA口座の開設者が亡くなった日以後、そのNISA口座で支払われるべき配当等があっても、非課税措置の適用外となります。
この場合、亡くなった時までの含み益については非課税措置の適用があります。(譲渡損失についてはなかったものとみなされます。)また、亡くなった日までに権利が確定した配当金・分配金についても非課税措置の適用があります。
相続人の口座へ移管後、売却した場合は課税口座での取引となり、相続した時点の基準価額と比較して値上がりしていれば、その利益については課税の対象となります。
また、亡くなった日の翌日以降に権利が確定した配当金・分配金については課税の対象となります。
相続対策としてNISAは有効?
相続対策としてNISAは有効なのでしょうか?相続人にとっては有利な場合もあれば不利な場合もあります。
有利な場合
被相続人が100万円で買付していた投資信託が、相続開始日に150万円になっていたとします。この投資信託を200万円で相続人が売却した場合について考えてみましょう。
被相続人が投資していた期間は非課税措置の適用範囲であり、非課税で運用されます。よって、相続開始日から売却した日までの売却益、つまり50万円が課税の対象となります。
不利な場合
被相続人が100万円で買付していた投資信託が、相続開始日に50万円になっていたとします。この投資信託を150万円で相続人が売却した場合について考えてみましょう。
この場合、被相続人が買付したときから実際には50万円分しか値上がりしていませんが、相続開始日から売却した日までの売却益に対して課税されるため、100万円が課税の対象となります。
NISA口座は損益通算もできないため、相続発生のタイミングによっては不利な場合もあるでしょう。
なお、取得費加算の特例が利用できる場合もあります。取得費加算の特例とは、相続した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる制度です。
相続対策として、NISAを使うことは必ずしも有効とは言い切れませんが、NISAを使って資産運用をすることで、非課税メリットを享受しながら資産を増やせる可能性はあります。相続人に対して資産を増やして相続したいと考えている場合、有効な手段なのではないでしょうか。
投資信託の相続が発生した時の注意点

投資信託の基準価額は変動する
投資信託の相続において最も気をつけるべき点は、投資信託の基準価額は変動するということです。相続発生日、遺産分割協議をスタートしたタイミング、移管をするタイミングで基準価額は異なります。
タイミングによっては、売却して換金した際に予想以上に手元に入る金額が少ないというケースも考えられるでしょう。相続人間のトラブルを防ぐためにも、売却して換金した資金は均等に分配するなどの対策が必要になります。
代償分割の場合に注意
代償分割とは、相続財産を分割する際、ある相続人が他の相続人へ代償金を支払うことで、特定の財産を取得する方法です。たとえば、不動産などの分割が難しい財産を相続する場合、不動産を取得する代わりに、該当の不動産の評価額と同等の金額を他の相続人へ支払うといった場合をいいます。
先述のとおり、投資信託の基準価額は変動するため、代償金の金額や評価を巡って、相続人間でトラブルとなるケースがあります。また、計算をするタイミングにも注意が必要です。
譲渡益が課税されることも
第4章でも触れたとおり、投資信託を相続したタイミングによっては、被相続人が投資信託を買付したときよりも基準価額が高くなっていて、譲渡益が課税対象となるケースがあります。
投資信託で資産を相続するメリットとは

投資信託で、資産を相続人へ引き継ぐことのメリットとはどんなものがあるのでしょうか?解説していきます。
分割が比較的容易である
たとえば不動産の財産分与は、分割が難しいといわれています。投資信託は口数で分割が可能であり、均等・公平な分配が可能です。
換金が容易である
換金ができなかったらどうしようと心配になることもあるでしょう。その点投資信託は流動性が高く、売買しやすいのが特徴です。基本的にいつでも買付でき、売却もいつでも可能です。売却金の入金には多くの場合2~5営業日かかるため、その点は考慮に入れて手続きをすすめましょう。
ファンドマネージャーが運用する
投資初心者の相続人が資産を引き継ぐことになっても、投資信託の運用はファンドマネージャーが行うため不安が軽減できます。
たとえば株式を相続した場合、投資初心者が売買の適正なタイミングを計るのはすぐには難しいでしょう。
分散投資
せっかく引き継いだ資産を大きく失うリスクは誰でも避けたいものです。
1つの銘柄に集中して投資していた場合、投資対象としている企業の業績悪化などの影響をそのまま受けてしまい、大きな損失を負う可能性があります。
投資信託は、複数の銘柄や対象に分散して投資します。複数の銘柄や対象に資金を分けて投資をすることで、リスクを分散し軽減することができます。
相続対策についてのご相談は投資信託相談プラザのIFAへ

今お持ちの資産をどういったかたちで次の世代に引き継ぐのか?お悩みの方はぜひ、IFAにご相談ください。
中立的な立場から資産運用のアドバイスができる
IFAは特定の金融機関に属していないため、中立的な立場で資産運用のアドバイスが可能です。IFAはお客様それぞれの年齢や目的などに合った商品を提案します。
相談料は無料
経験豊富な資産運用アドバイスのプロから相談を受けるのであれば、相談料が高いのでは?と不安に感じる人もいるかもしれません。
しかし、投資家がIFAに相談する際にかかる費用はありません。投資家が証券会社に支払う手数料の一部を証券会社経由で報酬として受け取るからです。また、同じ担当者から長期的なサポートを受けやすいのもIFAのメリットです。ひとりで悩まずに、気軽にご相談ください。
商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
投資信託に関するご注意事項
投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
取得の申し込みにあたっては投資信託説明書(目論見書)をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
NISAのご注意事項
・配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
・同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
・NISAで購入できる商品は金融商品取引業者が指定する商品に限られます。
・2024年からの新NISAでは年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
・損失は税務上ないものとされます。
・出国により非居住者に該当する場合、原則としてNISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
・2024年からの新NISAにおけるつみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
※その他、2024年からの新NISAに関するご注意事項、並びに2023年までの一般NISA ・つみたてNISA等に関するご注意事項の詳細は金融商品取引業者のWEBサイトにてご確認ください。
その他のご注意事項
税務に関する相談は、必ず税理士に行ってください。
このコラムの執筆者

道谷 昌弘
株式会社Fan IFA
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

































































AFP(日本FP協会認定) 大学卒業後、大手証券会社に入社。国内営業部門にて法人・個人の資産運用アドバイスを行う。8年間勤めたのち退社し、より中立的なアドバイスができるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。現在は富山を拠点に、全国各地のお客様に幅広くコンサルティングを行いながら、お客様にとって本当に良い商品提案を日々追求している。