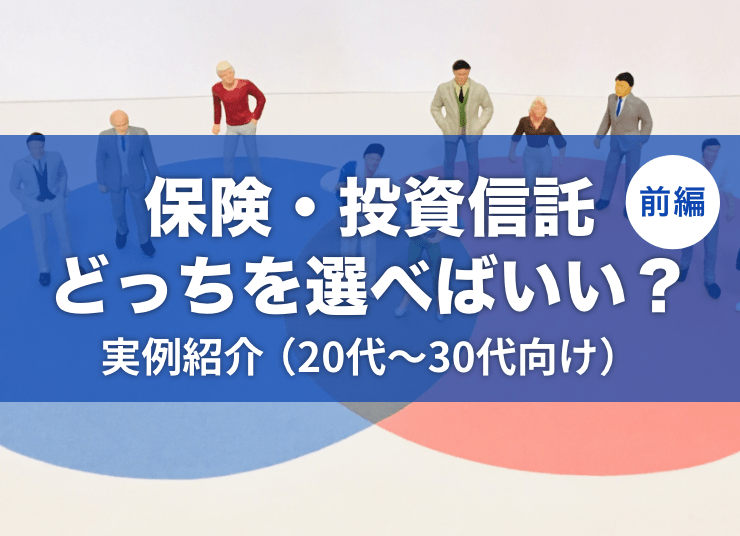
資産運用の方法を検討するうえで、保険と投資信託、どちらを選んだらいいか悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
投資において、「卵は一つのカゴに盛るな」という言葉はよく知られています。これは、一つの投資先に集中することで、その投資先が不調に陥った際に大きな損失を被るリスクを分散させるために、複数の投資先に分散して投資を行うべきだという考え方です。
投資先の分散も大切ですが、異なる種類の金融商品に投資する「金融商品の分散」もおすすめです。
複数の金融商品を組み合わせて投資することで、リスクを分散し、より安定したポートフォリオを構築することができます。
さまざまな金融商品を「併せ持ち」することで、単独で商品を保有するよりもリスクを抑えたり、リターンを向上させ、より効率的な運用に期待できるのではないでしょうか?
投資信託相談プラザのIFAが提案した事例を参考に、前後編に分けてお話していきます!
「これから資産運用を始めたい!」そんな方へ

資産運用の基本や運用のコツ、活用したい制度や実践方法など、資産運用の基礎をまるごと学べるハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
INDEX
変額保険×投資信託〈20代・女性の場合〉

20代の女性の方のご相談です。
「積立投資をしたいと思っています。積立型の変額保険と投資信託ではどちらが良いと思いますか?」
- 20代女性
- 年収400万円
- 結婚歴なし/子どもはいない
- 資産運用はしていない
それでは、回答をみていきましょう。
IFAの提案:どちらも保有して頂くことをおすすめします
ご質問ありがとうございます!お客様の状況・考え方によっても変わりますが、どちらも保有して頂くことをおすすめします。
理由は、投資信託も変額保険も、それぞれ特性があり、それぞれに保有するメリットがあるからです。
商品選択の基準は、お客様の状況や考え方によって大きく変わってきます。両方を組み合わせることで、よりバランスの取れた資産形成が可能になるケースも少なくありません。
今回のご質問では、投資信託と積立型の変額保険を検討しておられるとのこと。まずは、投資信託のメリットをみていきましょう!
投資信託のメリットとは
- 商品によっては、コストを抑えて運用することができる
- NISAを利用することができる
- 最低投資金額が100円からで、気軽にスタートできる
投資信託は、低コストで無理なく始められる投資方法であるところがポイントです。20代でまだ投資初心者という質問者様にはおすすめの商品です。ノーロードの投資信託を選べば、購入時手数料がかかりません。
購入時手数料がかからない場合でも、運用期間中の信託報酬と解約時の信託財産留保額がかかることがあるため、購入前にチェックしておきましょう。投資信託の手数料や費用はファンドごとに異なり、手数料等の差で得られる利益に大きな差が出てきます。
また、投資信託は運用のプロが投資家に代わって運用してくれるため、気軽に始めることができます。
投資信託は一部の銘柄を除き、NISAを使って購入することができます。税制上の優遇を受けながら、効率的に資産形成を進めるうえで有効です。
次に、変額保険についてみていきましょう。
変額保険のメリットとは
- 死亡保険金・高度障害保険金などの保障がある
- 保険料払込免除特約がある
- 生命保険料控除が使える
- 相続税対策として有効(ex.死亡保険金の非課税枠など)
変額保険は、保障と資産形成の両方を叶えたい方にぴったりです。
所定の高度障害になったときは、保険金が支払われます。また、三大疾病保険料払込免除特約(※)をつけることで、商品にもよりますが、がん・心疾患・脳血管疾患の診断が確定した場合には、保険料の払い込みが免除されます。
※保険会社により条件は異なりますが、三大疾病で所定の条件になった時に保険料の払込を免除してくれるオプションです。
変額保険では契約者が払った保険料を原資として、金融商品に投資しています。
金融商品の内容は、株式や債券などがあげられます。運用の実績に応じて保険金や解約返戻金が変動します。契約者が死亡した際は、基本保険金に上乗せして変動保険金を受け取れる場合があります。運用実績により変動保険金がマイナスになっても、基本保険金額は最低保証されます。
保険期間は大きく2種類あります。
- 有期型(一定期間保障される)
- 終身型
「有期型」「終身型」とも、解約返戻金に最低保証はありません。
✅インフレに強い変額保険
変額保険のメリットとして、「インフレに強い」点があげられます。
インフレ環境下では物価が上昇するため、死亡保険や年金額が契約時のまま変わらなければ、受け取り時に手元に入る金額が少ないと感じる可能性があります。
変額保険は金融商品で運用しているので、相場環境が良ければ保険金額が増える可能性があります。
✅デフレには弱い変額保険
逆に「デフレには弱い」という点がデメリットといえます。
運用成績が悪くなると、定額型の保険と比較して保険料が割高になることもあるでしょう。
変額保険は投資初心者には保険の仕組みやリスクを理解する事が難しいかもしれません。契約前には組み入れている資産の種類やその評価方法、運用方針、運用実績によって将来受け取る保険金などの額がどう変動するのか、しっかりと説明を求めましょう。
変額保険などの金融商品で運用するタイプの保険は、投資信託と比較すると死亡保障などの費用がかかるため、運用コストがかかります。純粋に投資実績だけを追求するならば、投資信託の方が合理的かもしれません。
ただ変額保険には先述のとおり、充実した保障や保険料控除を使えるなどのメリットがあります。
投資信託だけではカバーできないリスクを変額保険を併せ持ちすることで補うことができます。次のケースで、どのようにリスクを補うことができるのかをみていきましょう。
変額保険×投資信託〈30代・男性の場合〉

30代男性のケースです。
「30歳のときにがんと診断されました。就職したタイミングから投資信託の積立と積立型の変額保険への払い込みを続けてきて良かったです。」
併せ持ちで得られたメリットとは
さて、この方はなぜ、2つの商品を併せ持ちしてきて良かったと感じているのでしょうか?詳しくみていきましょう。
- 20歳のときに積立型の変額保険に加入(保険料払込期間・30年/毎月払1万円)10年間払込している
- 先進国株式インデックスファンドを10年間(毎月1万円)買付している
この方の場合、30歳時点で10年間の投資信託の積立総額は120万円です。積立型の変額保険は同様に120万円を払い込んでいます。
変額保険に三大疾病保険料払込免除特約を付帯していたので、健康であれば支払う必要があった240万円(残り20年分の保険料)を支払う必要がなくなりました。これによって病気による収入減により全ての積立が止まってしまうリスクを避けることができました。
がんは、三大疾病の中でも特に罹患率が高く、2人に1人がかかるといわれています。
この方が老後の資産準備を目的として積立をしていた場合、就労が難しくなれば予定の金額に達しない可能性があります。変額保険で保険料払込免除特約を付帯している場合、がんになって就労が難しく以後の保険料が払えなくなったとしても、予定よりは少なくなりますが、老後資金を準備することができます。
もし毎月の積立金額に余裕があるようなら、金融商品を組み合わせて使うことでさまざまなリスクに対応することができるのでおすすめです。
実際どのような割合で運用しているの?
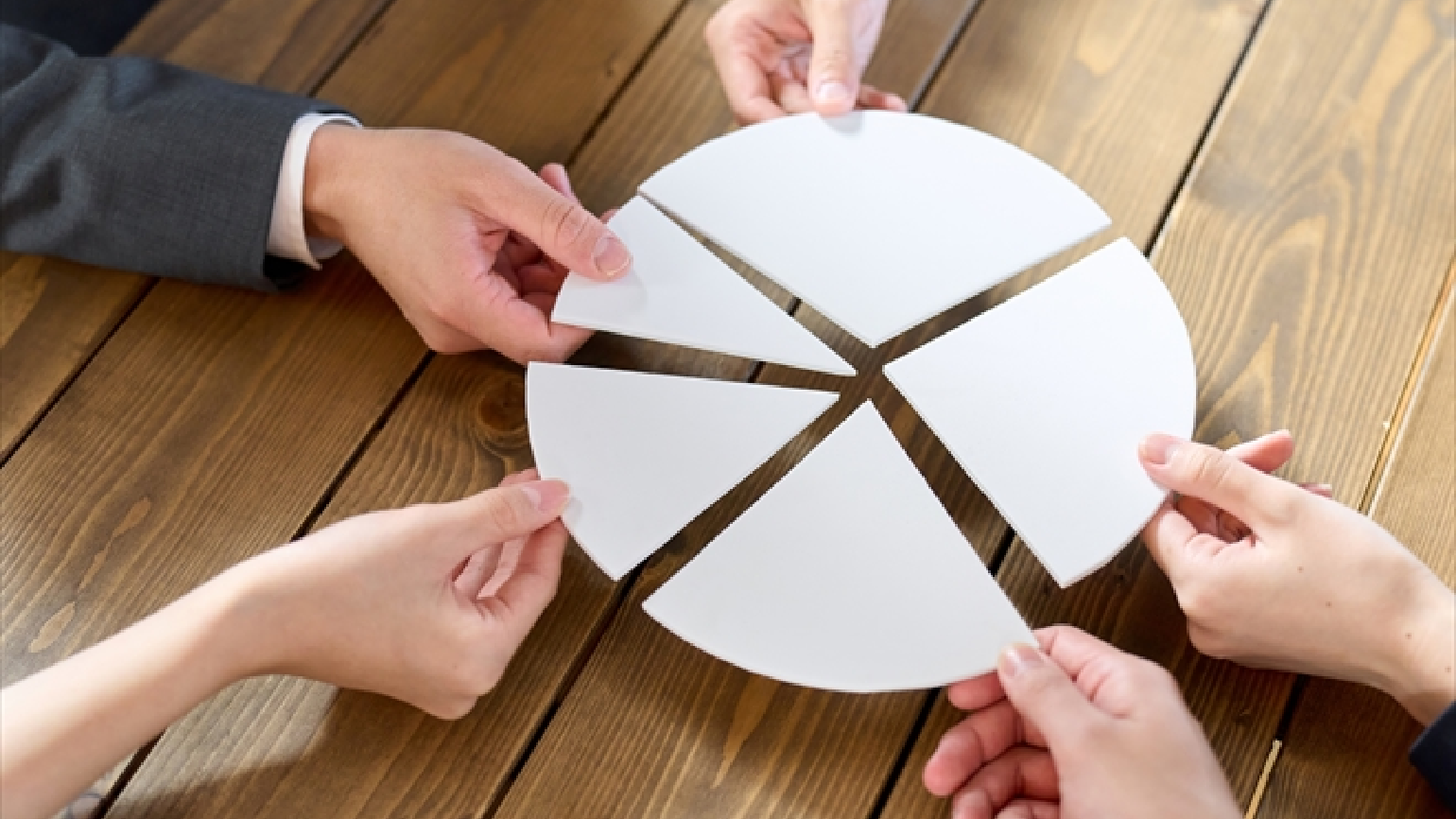
毎月5万円の積立を検討しているお客様へのご提案事例です。
IFAの提案:保険と投資のバランスをとりましょう
- バランス型の投資信託(毎月2万円)NISAのつみたて投資枠を利用して買付
- 先進国株式インデックスファンド(毎月2万円)NISAのつみたて投資枠を利用して買付
- 積立型の変額保険 保険料払込期間30年(毎月1万円)
合計:毎月5万円
この方は純粋に投資実績を追求したいということもあり、収益率が期待できる株式インデックスファンドも取り入れつつ、老後のリスクに備えて積立型の変額保険も組み合わせて使うことになりました。
また、一般生命保険料控除の上限額に達しておられなかったことも、変額保険を選択するきっかけとなりました。保険料控除を使えば年末調整で毎年所得税・住民税の負担が軽減されます。
保険は目的をもって加入することが大切です。お持ちの保険内容と目的が合致していることで、財産を守ることにつながります。先述した30歳の男性のケースでも、全て投資信託で運用していた場合、計画通りに資産形成が叶わないかもしれません。
- 「ため」の備え
- 必ず必要になるものへの備え(教育費・老後資金)
- 「もしも」への備え
- 必要かはわからないものに対する備え
私たちが普段思い描いているのは、これまで通り健康で仕事ができ、何事もなく過ごせた場合のライフプランです。
しかし、人生は思い通りにいかないものです。病気やケガ、失業など、様々なリスクがつきまといます。もしもの時に備えて、保険でリスクをカバーしておくことは非常に重要です。しかし、投資性の保険のみで投資実績を追求しようとしたとすれば、運用コストがかさむなどのデメリットも考えられます。
投資信託で資産を増やしつつ、保険でリスクをカバーするという考え方は、まさに将来設計においてバランスの取れた戦略といえるのではないでしょうか?
保険・投資、一人ひとりのライフプランにあわせて適切な選択を

さまざまな保険がありますが、目的に合った保険設計ができているかが大切です。またライフステージごとに必要な保障は変わります。必要以上な保障がないかチェックしましょう。
投資をする際も投資先を分散させることをおすすめします。
併せ持ちする変額保険の特別勘定の運用方針を確認することが大切です。特別勘定の運用方針が、「バランス型で株式の組み入れ比率は3割以下、外貨建て資産の組み入れ比率は3割以下」という方針であれば、併せ持ちする投資信託は外国株式に投資するファンドを選択してもいいかもしれません。
投資信託相談プラザのIFAは、特定の証券会社・保険会社に限定せず、複数の金融機関の中から商品を提案いたします。お客様から相談料を頂くことは一切ございませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい
弊社の生命保険募集人は、保険契約の締結にあたり保険会社の承諾を必要とする媒介の権限のみが認められており、契約締結の代理権や告知受領権はありません。保険契約の申込をされる際は、ご契約のしおり、約款、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、契約締結前交付書面等の書面を十分にご確認くださいますようお願い申し上げます。また、変額保険には運用リスク等のリスク、外貨建て保険には為替リスク等のリスクがございます。リスクや手数料等の重要事項をよくご確認ください。
各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
投資信託に関するご注意事項
投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
取得の申し込みにあたっては投資信託説明書(目論見書)をお渡ししますので、必ずファンドの仕組みやリスク等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
NISAのご注意事項
・配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
・同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
・NISAで購入できる商品は金融商品取引業者が指定する商品に限られます。
・2024年からの新NISAでは年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
・損失は税務上ないものとされます。
・出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
・2024年からの新NISAにおけるつみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
※その他、2024年からの新NISAに関するご注意事項、並びに2023年までの一般NISA ・つみたてNISA等に関するご注意事項の詳細は金融商品取引業者のWEBサイトにてご確認ください。
このコラムの執筆者

MONEY HUB PLUS 編集部
株式会社Fan
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

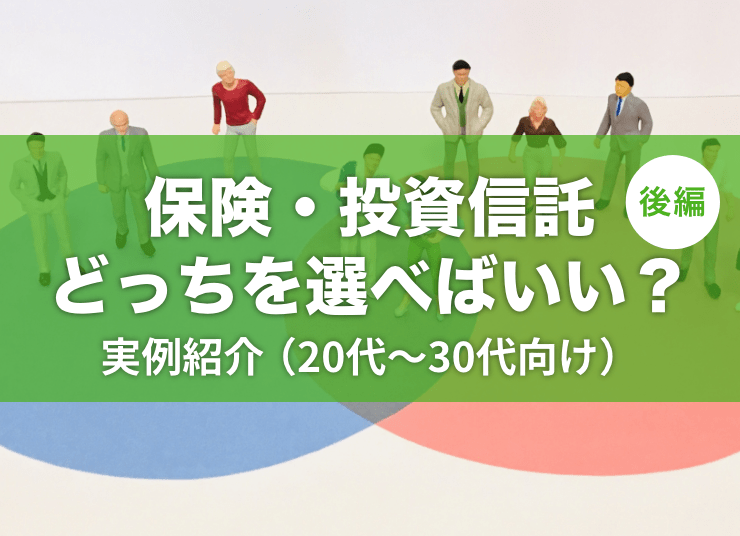
































































未来につながる投資情報メディア「Money Hub Plus(マネハブ)」の編集部です。
みなさまの資産形成に役立つ情報を日々発信しております。