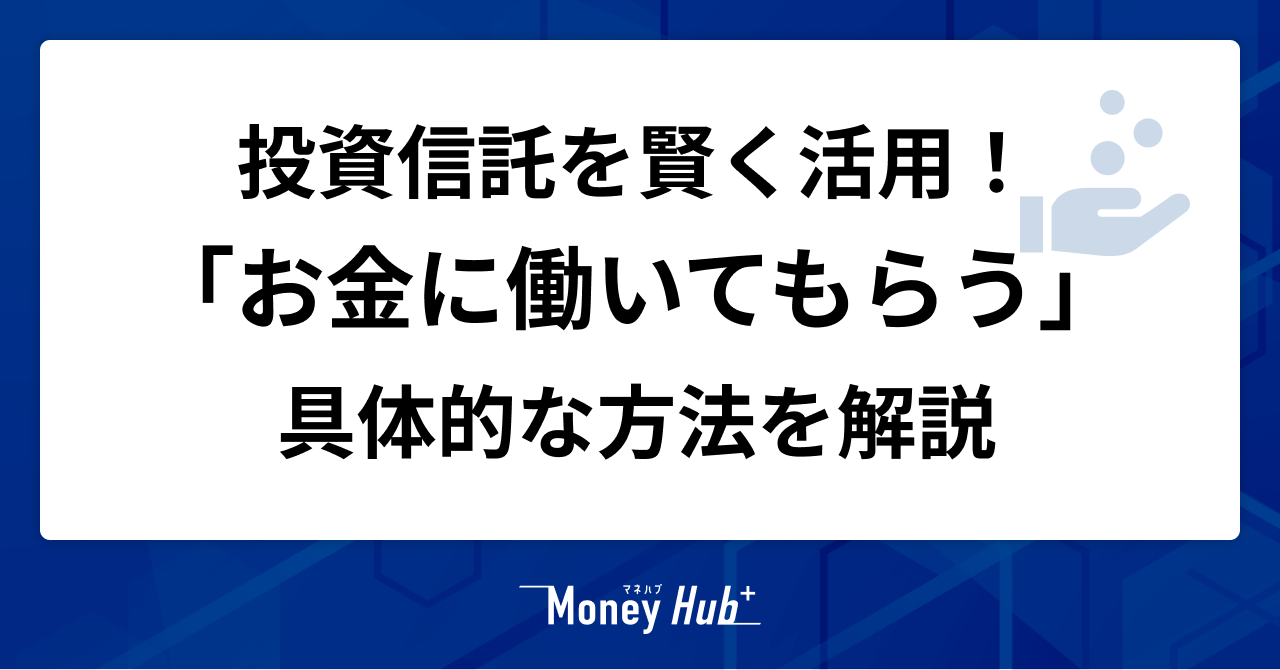
この記事のポイント
- 初心者が「お金に働いてもらう」には、少額から始められ、ファンドマネージャーが運用する「投資信託」が有力な選択肢
- NISA制度を活用すれば、税金の優遇を受けながら資産運用ができる
- 始める際は、「余裕資金」で行い、「長期・積立・分散」を心掛けることが大切
「将来のために貯金はしているけれど、銀行に預けているだけではほとんど増えない…」
「老後2,000万円問題なんて言葉も聞いたし、このままで大丈夫なのかな…」
もしあなたがこのように感じているなら、ぜひ「お金に働いてもらう」という考え方を知ってください。
かつて銀行預金の金利が高かった時代は、ただ貯金をしているだけでお金は着実に増えていきました。しかし、現代は歴史的な低金利時代。同じ方法では、資産を効率的に増やすことは難しくなっています。
お金自身が働いてくれる「資産運用」は、あなたが眠っている間も、遊んでいる間も、あなたに代わってお金を増やしてくれる可能性があります。
「資産運用なんて、難しそうだし怖い…」と感じるかもしれませんが、この記事が、 あなたの疑問や不安を解決へ導く手助けとなります!
資産運用の経験がない初心者の方でも気軽に始めやすい「投資信託」を活用して、「お金に働いてもらう」ための具体的な方法を、専門用語をかみ砕きながら分かりやすく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、「自分にもできそう!」と、将来に向けた資産形成の第一歩を踏み出す準備が整っているはずです。
「NISAを使って資産運用を始めたい!」そんな方へ
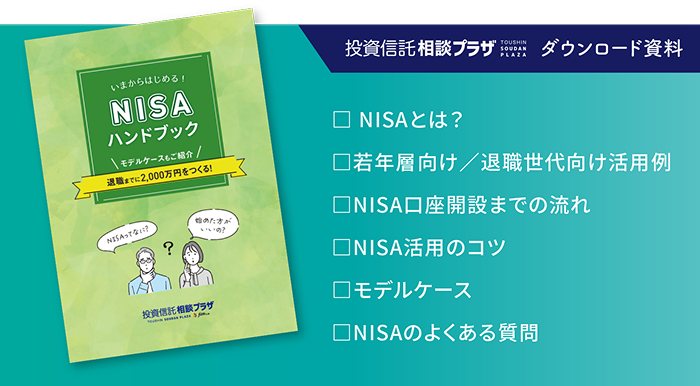
NISA(少額投資非課税制度)のしくみや活用のコツ、実際の活用例などをまとめたハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
INDEX
なぜ今「お金に働いてもらう」必要があるのか?2つの理由
そもそも、なぜ今「お金に働いてもらう」ことが、これほどまでに重要なのでしょうか。その背景には、私たちの生活に直結する2つの大きな経済的な理由があります。
理由1:銀行預金ではお金が増えない「低金利時代」
現在の銀行の普通預金金利がどのくらいかご存じでしょうか?
多くの金融機関では、年0.2%程度(2025年9月時点)という、低金利が続いています。 これは、100万円を1年間預けても、利息はわずか2,000円(税引前)にしかならない計算です。
かつては、銀行の預金金利が5%を超えていた時代もありました。その頃は、預けておくだけでお金が着実に増えていきました。しかし、低金利が続く現代では、預貯金だけで資産を大きく増やすことは非常に難しくなっています。
出典:円預金金利|三井住友銀行 円預金金利|三菱UFJ銀行 預金金利・利率|みずほ銀行
理由2:持っているお金の価値が減る「インフレ」のリスク
「インフレ(インフレーション)」という言葉を聞いたことがありますか? これは、モノやサービスの値段(物価)が上がり続け、相対的にお金の価値が下がってしまう現象のことです。
例えば、昨年まで100円で買えていたお菓子が、今年110円に値上がりしたとします。 これは、モノの値段が10%上がった(インフレ率10%)と同時に、あなたのお財布に入っている100円玉の価値が、お菓子1個分から0.9個分に目減りしたことを意味します。
総務省統計局が発表している「消費者物価指数」を見ると、近年、私たちの身の回りの様々なモノやサービスの価格が上昇傾向にあることがわかります。
もし、物価が年2%のペースで上昇し続けると、現在100万円で買えるものが、10年後には約122万円、20年後には約149万円を支払わないと買えなくなる計算です。 銀行に預けたままの100万円は、残高は変わらなくても、実質的な購買力(価値)はどんどん下がってしまうのです。
この「低金利」と「インフレ」という2つの課題に対抗し、お金の価値を守り、さらに増やしていくために、「お金に働いてもらう」=資産運用が不可欠な時代と言えるのです。
「資産運用を体系的に学びたい!」そんな方へ

私たち「投資信託相談プラザ」は、毎月全国各地・オンラインにて資産運用セミナーを開催しています。(参加費無料)
参加者数は延べ70,000人超(※)。ぜひお気軽にご参加ください!
※2015年12月~2025年7月末までの実績
\ SBI証券 共催・楽天証券 協賛 /
初心者が「お金に働いてもらう」なら投資信託が有力な選択肢となる理由
「資産運用の必要性はわかったけれど、具体的に何をすればいいの?」 そう思われた方に、まず検討をおすすめしたいのが「投資信託」です。
投資信託が、特に初心者にとって有力な選択肢となる4つの理由をご紹介します。
理由1:1,000円程度の少額から始められる
投資と聞くと、まとまった資金が必要なイメージがあるかもしれませんが、投資信託の多くは月々1,000円や100円といった少額から積立投資を始めることができます。
毎月のお小遣いや、節約で浮いたお金の一部からでもスタートできるため、「まずは無理のない範囲で始めてみたい」という方でも、心理的・金銭的なハードルが非常に低いのが魅力です。
理由2:専門家であるファンドマネージャーが運用
投資信託は、「投資家から集めた資金を一つの大きな資金としてまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに投資・運用する金融商品」です。
どの会社の株を買うか、いつ売るかといった判断はすべて専門家が行ってくれるため、投資に関する詳しい知識や、市場を常にチェックする時間がない忙しい方でも、資産運用を始めることができます。
理由3:自然とリスク分散ができる仕組み
投資の世界には、「卵は一つのカゴに盛るな」という有名な格言があります。 これは、一つの資産に集中投資すると、それが値下がりしたときに大きな損失を被ってしまうため、複数の資産に分けて投資することでリスクを分散しましょう、という意味です。
多くの投資信託は、一つの商品の中に国内外の様々な株式や債券などが組み入れられており、その数は数十から数千に及ぶものもあります。そのため、投資信託を1本買うだけで、手軽に様々な国や資産への分散投資につながる点が大きな魅力です。
理由4:NISA(ニーサ)制度で税金の優遇も
通常、投資で得られた利益(配当金、分配金、譲渡益)には約20%の税金がかかります。 しかし、「NISA(ニーサ)」という国の税制優遇制度を活用すれば、一定の投資額まで、この税金が非課税になります。
2024年にNISA制度がリニューアルされ、旧制度よりも非課税で投資できる上限額が大幅に拡大されました。これにより多くの人がこの非課税のメリットを享受できるようになりました。
せっかく「お金に働いてもらう」のであれば、この制度を使わない手はありません。
あわせて読みたい
押さえておきたい!投資信託でお金に働いてもらうための簡単4ステップ
では、実際に投資信託を始めるにはどうすればよいのでしょうか。 ここでは、具体的な4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:目標を決める
まず最も大切なのが、「何のために、いつまでに、いくら必要か」という具体的な目標を設定することです。
- 「30年後に、ゆとりある老後資金として2,000万円貯めたい」
- 「15年後に、子どもの大学進学費用として500万円作りたい」
- 「10年後に、車の買い替え費用として300万円用意したい」
このように目標を明確にすることで、毎月いくら積み立てるべきか、どの程度のリスクを取るべきか、といった運用方針が見えてきます。
金融庁のウェブサイトにある「つみたてシミュレーター」などを活用すると、毎月の積立額や想定利回り、積立期間を入力するだけで、将来いくらになるかを簡単に試算できます。ぜひ一度、ご自身の目標を立てる参考にしてみてください。
あわせて読みたい
ステップ2:どの投資信託を購入するか選ぶ
数千本以上ある商品の中から一つを選ぶのは大変に感じるかもしれませんが、初心者の方はまず以下の2つのポイントで絞り込むと良いでしょう。
- 手数料(信託報酬)が低い商品を選ぶ
- 信託報酬とは、投資信託を保有している間、継続的にかかるコストのことです。
- この手数料は、長期的に見るとリターンに大きな差を生むため、できるだけ低い商品(目安として年率0.2%以下)を選びましょう。
- 幅広い地域に分散投資できる商品を選ぶ
- 日本だけでなく、全世界の株式にまとめて投資できる「全世界株式(オール・カントリー)」や、世界経済の中心である米国企業に投資する「S&P500」といった指数に連動するインデックスファンドが、初心者には人気です。
ステップ3:証券会社の口座を開設する
投資信託は、主に証券会社や銀行で購入することができます。それぞれの特徴を理解して、自分の目的に合わせて金融機関を選びましょう。
ネット証券は品揃えが豊富で手数料も安価なことが多いのでおすすめです。また、NISA口座は1人につき1口座しか開設できないため、慎重に検討しましょう。
口座開設は、スマートフォンやパソコンからオンラインで完結する場合がほとんどです。本人確認書類(マイナンバーカードなど)と銀行口座があれば、10分程度の入力作業で申し込みが完了します。
あわせて読みたい
ステップ4:投資信託を選んで金額を入力し発注
購入したい商品を選び、「毎月」「1万円」のように、積立金額と購入日を設定します。
一度設定すれば、あとは自動的に毎月決まった日に決まった金額を買い付けてくれるので、手間がかからず、感情に左右されずにコツコツと投資を続けることができます。
「ネット証券での資産運用を相談したい!」そんな方へ

私たち「投資信託相談プラザ」はSBI証券・楽天証券と提携しており、仲介口座数は延べ60,000口座、仲介する預かり資産残高は4,500億円超の実績があります。(※)
全国各地の店舗・またはオンラインで無料相談できます。お気軽にご利用ください!
※令和7年12月時点
\ SBI証券・楽天証券 提携窓口 /
【注意】お金に働いてもらう前に知っておきたい3つの心構え
ここまで投資信託のメリットや始め方をお伝えしてきましたが、もちろん注意点もあります。 「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、始める前に以下の3つの心構えをしっかりと理解しておきましょう。
1. 元本保証ではないことを理解する
最も重要な点は、投資信託は預金とは異なり、元本が保証されていないということです。 投資先の株式や債券の価格は日々変動するため、購入した時よりも価値が下がり、元本割れ(投資した金額を下回ること)する可能性があります。
必ず、生活費や近い将来に使う予定のあるお金ではなく、当面使う予定のない「余裕資金」で行うようにしましょう。
2. 短期的な値動きに一喜一憂しない
投資信託の基準価額は、世界経済の動向などによって日々上下します。 始めたばかりの頃は、基準価額が少し下がっただけでも不安になって売りたくなってしまうかもしれません。
しかし、資産運用で成果を出すためには、短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点でコツコツと積立を続けることが何よりも大切です。基準価額が下がっているときは、むしろ「安くたくさん買えるチャンス」と捉えるくらいの気持ちでいることが成功の鍵となります。
3. 手数料(コスト)を意識する
ステップ3でも触れましたが、投資信託には以下のような手数料がかかります。
- 購入時手数料: 購入時にかかる手数料(無料の「ノーロード」商品もあります)
- 信託報酬(運用管理費用): 保有期間中に毎日かかるコスト
- 信託財産留保額: 売却時にかかる手数料(かからない商品もあります)
商品を選ぶ際には、必ずこの信託報酬がどのくらいかをチェックする習慣をつけましょう。
「自分一人では不安…」その悩み、IFAへの相談が解決の近道
ここまで読み進めて、「自分でも始められそう!」と感じた方もいれば、「やっぱり一人で商品を選ぶのは不安…」「自分に合った目標設定や運用プランがわからない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は、資産運用のアドバイザーに相談するという選択肢があります。
アドバイザーに相談することで、
- たくさんの情報の中から、自分に必要な情報だけを得られる
- 自分の収入や家族構成、将来の目標に合った、具体的なプランを提案してもらえる
- わからないことや不安なことを、その場で直接質問して解消できる
といったメリットがあり、時間や手間をかけずに、無理なく資産運用の第一歩を踏み出すことができます。
私たち「投資信託相談プラザ」では、知識と経験豊富なIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、中立的な立場でお客様の資産運用をサポートしています。 無理な勧誘などはいたしませんので、まずはお気軽に、あなたの将来のお金に関するお悩みをお聞かせください。
あわせて読みたい
まとめ:投資信託で「お金に働いてもらう」第一歩を踏み出そう
この記事では、投資信託を活用して「お金に働いてもらう」ための具体的な方法について解説しました。 最後に、今回の重要なポイントを振り返ります。
- 「低金利」と「インフレ」の時代、貯金だけではお金の価値は目減りしていく可能性がある
- 初心者が「お金に働いてもらう」には、少額から始められ、ファンドマネージャーが運用する「投資信託」が有力な選択肢
- NISA制度を活用すれば、税金の優遇を受けながら資産運用ができる
- 始める際は、「余裕資金」で行い、「長期・積立・分散」を心掛けることが大切
- 一人で始めるのが不安な場合は、アドバイザーに相談するのも有効な手段
「お金に働いてもらう」ことは、もはや特別なことではなく、将来を豊かに生きるための必須スキルになりつつあります。 この記事が、あなたが大切な資産を守り、育てるための第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
「NISAを使って資産運用を始めたい!」そんな方へ
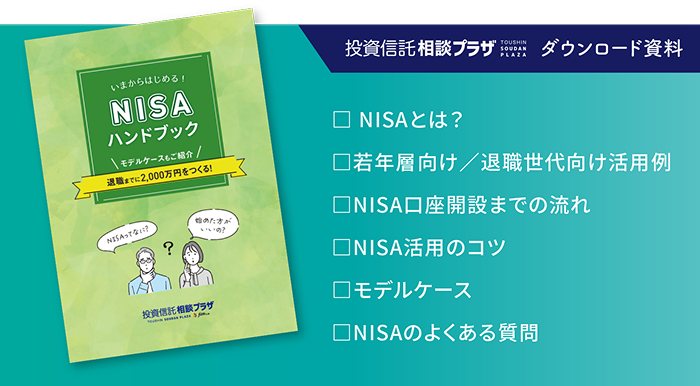
NISA(少額投資非課税制度)のしくみや活用のコツ、実際の活用例などをまとめたハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
このコラムの執筆者

MONEY HUB PLUS 編集部
株式会社Fan
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。





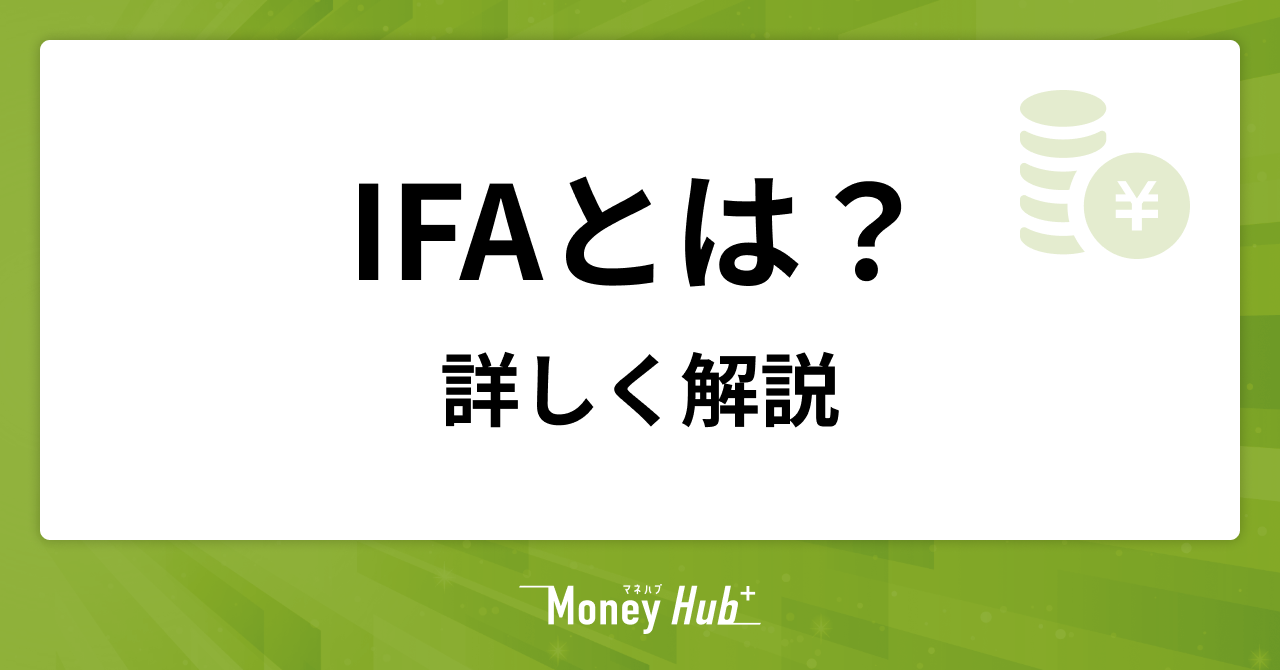




























































未来につながる投資情報メディア「Money Hub Plus(マネハブ)」の編集部です。
みなさまの資産形成に役立つ情報を日々発信しております。