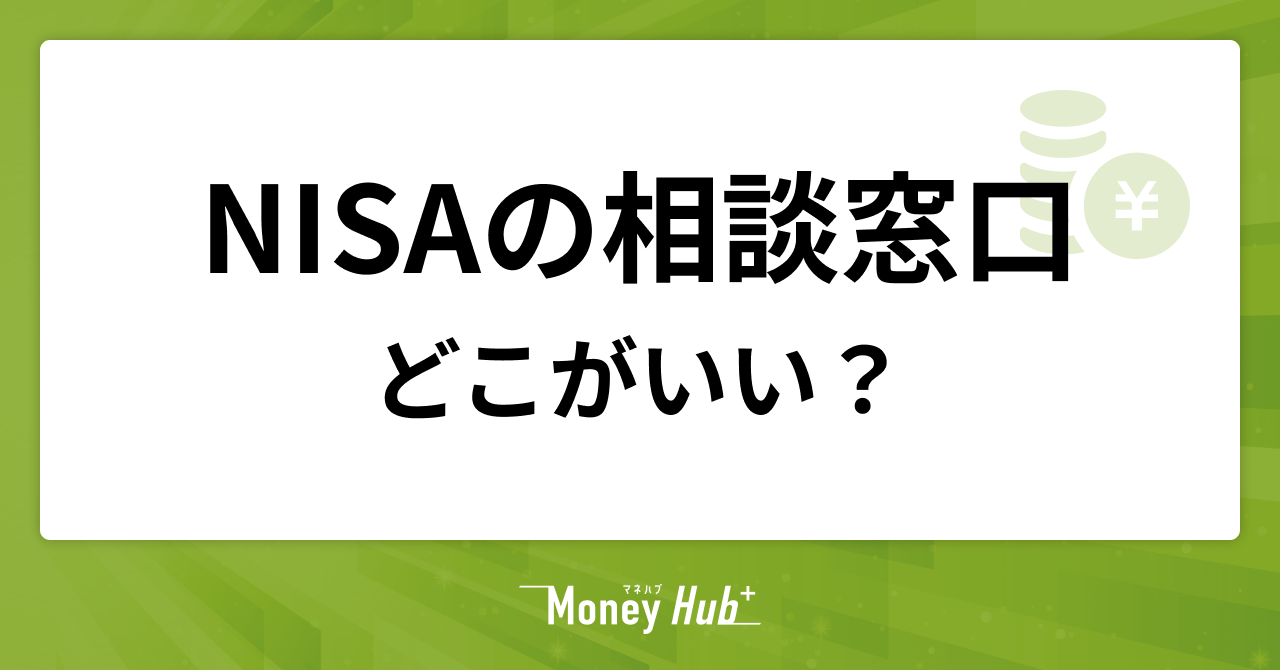
この記事のポイント
- NISAの相談窓口には、銀行・証券会社・IFA・保険会社・公的機関などが挙げられる。
- 相談内容を事前に整理すれば、どの窓口に相談すべきかが見えてくる。
- その他に、「現在の収入」「資産状況」「将来のライフプラン」「NISAに関する疑問点」を事前に整理しておくと良い。
「NISA(ニーサ)制度が新しくなったと聞いたけど、資産運用なんてやったことないし、何から始めればいいんだろう…」
「自分なりに調べてみたけれど、専門用語も多くてよく分からない…」
将来のための資産形成に関心が高まる中、NISA制度を活用してみたいと考える方は増えています。 しかし、いざ始めようと思っても、制度の仕組みや商品の選び方など、疑問や不安を感じることも少なくないでしょう。
特に、お仕事や家事で忙しい日々を送る中で、ご自身だけで情報収集から実践までを行うのは時間的にも精神的にも負担が大きいかもしれません。
この記事では、NISAに関する相談ができる主な窓口の種類と、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。 さらに、ご自身に合った相談先を見つけるためのポイントや、相談前に準備しておくと良いことなどもご紹介します。
NISAに関する疑問を解消し、資産形成の第一歩を踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。
「ネット証券での資産運用を相談したい!」そんな方へ

私たち「投資信託相談プラザ」はSBI証券・楽天証券と提携しており、仲介口座数は延べ60,000口座、仲介する預かり資産残高は4,500億円超の実績があります。(※)
全国各地の店舗・またはオンラインで無料相談できます。お気軽にご利用ください!
※令和7年12月時点
\ SBI証券・楽天証券 提携窓口 /
INDEX
専門家への相談がおすすめな理由 – 不安解消とあなたに合ったプランが見つかる可能性
専門家に相談することで、以下のようなメリットが期待できます。
- NISA制度や金融商品に関する正確な情報を得られる
NISAの基本的なことや商品の内容を分かりやすく解説してもらい、正しい知識を身につけることができます。 - 個別の状況に合わせたアドバイスを受けられる
ご自身の収入や資産状況、ライフプラン、リスク許容度などを踏まえた上で、具体的な運用プランや商品選定についてのアドバイスが期待できます。 - 疑問や不安の解消につながる可能性がある
インターネットや書籍だけでは解決しきれない細かな疑問点や、個人的な不安について直接質問することで、問題が解消できるかもしれません。 - 時間的な負担を軽減できる
自分で情報収集する手間を省き、必要な知識や情報を効率的に得ることができます。 - 客観的な視点からの意見を聞ける
自分一人で考えると偏りがちな判断も、専門家の客観的な意見を聞くことで、より冷静に検討できるようになるでしょう。
NISAの相談ができる主な窓口5選 –それぞれの特徴・メリット・デメリットを比較
1. 銀行 – いつもの取引先で気軽に相談できる
普段から給与振込や公共料金の引き落としなどで利用している銀行は、最も身近な相談窓口の一つと言えるでしょう。
メリット
- 普段利用している
日常的に接しているため、心理的なハードルが低く、気軽に相談しやすいと感じる方が多いでしょう。 - 対面相談のハードルの低さ
多くの銀行が店舗窓口を設けており、直接顔を見て相談できます。 - 他の金融サービスと合わせて相談しやすい
預金や住宅ローンなど、他の金融サービスと合わせてライフプラン全体の相談ができる場合もあります。※住宅ローンのサービスとは窓口が異なる場合がございます
デメリット
- 取扱商品が系列会社のものに偏る可能性
銀行が取り扱うNISA対象商品は、その銀行の系列運用会社が設定・運用する投資信託が中心となる傾向があります。そのため、選択肢が限られる場合があります。
2. 証券会社(対面営業) – 豊富な商品知識と多様な選択肢
株式投資や投資信託など、本格的な資産運用サービスを提供している証券会社も、NISA相談の主要な窓口です。
メリット
- NISA口座開設から運用まで一貫サポート
NISA口座の開設はもちろん、その後の運用に関する専門的なアドバイスや情報提供が期待できます。 - 専門的なアドバイス
資産運用についての知識のある担当者から、より専門的なアドバイスを受けられる可能性があります。 - 幅広い金融商品
投資信託だけでなく、国内外の株式など、銀行に比べて多様な金融商品を取り扱っているため、投資対象の選択肢が広がります。
デメリット
- 敷居が高いと感じる人も
これまで投資経験がない方にとっては、証券会社の窓口は少し敷居が高いと感じられるかもしれません。※店舗を持たないネット証券の場合は、基本的に個別商品に関する投資判断はお伝えしないところが多く、お客様ご自身の判断でお取引いただくことになります。
3. IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー) – 中立的な立場からのアドバイスに期待
IFA(Independent Financial Advisor)とは、特定の金融機関に所属せず、独立した立場で顧客に資産運用のアドバイスを行う専門家です。
メリット
- NISA口座開設等のサポート
業務提携している金融機関のNISA口座開設サポート等が受けることができます。 - 特定の金融機関に属さず、幅広い選択肢から提案を受けられる可能性
特定の金融機関の商品に縛られず、複数の金融機関の商品の中から、相談者のニーズに合ったものを中立的な視点から提案してくれることが期待できます。 - 長期的な視点でのサポート
転勤などが少ないため、同じ担当者から長期にわたってサポートを受けやすい傾向があります。ライフステージの変化に応じた見直し相談もしやすいでしょう。 - 相談者の意向を重視したコンサルティング
お客さま本位の丁寧なコンサルティングが期待できます。
デメリット
- アドバイザーによって専門性や得意分野に違いがある
IFAと一口に言っても、その知識レベルや得意とする相談内容は様々です。信頼できるIFAを見つけるためには、情報収集や比較検討が重要になります。 - 認知度がまだ高くない
銀行や証券会社に比べると、IFAの存在自体を知らないという方もいるかもしれません。
あわせて読みたい
4. 保険会社・保険代理店 – 保険とセットで検討したい場合に
生命保険会社や保険代理店の窓口でも、NISAに関する相談ができる場合があります。これは、生命保険会社や保険代理店が金融商品仲介業者として、証券会社等である金融商品取引業者又は登録金融機関と業務委託契約を結んでいるケースです。 特に、保険商品と組み合わせて資産形成を考えている場合に選択肢の一つとなるでしょう。
メリット
- 生命保険などと合わせて資産形成の相談ができる
既に保険の相談をしている担当者がいれば、その流れでNISAについても相談しやすいかもしれません。保険とNISAを組み合わせたライフプランニングの提案を受けられる可能性があります。
デメリット
- NISAの取扱商品が限定的である可能性
保険会社や代理店が取り扱うNISA対象商品は、提携している運用会社のものに偏るなど、選択肢が少ない場合があります。 - 保険商品の提案が中心になることも
あくまで保険の専門家であるため、NISAよりも保険商品の提案に重点が置かれる可能性があります。NISAに関する専門的なアドバイスが十分に得られないケースも考えられます。
5. 公的機関・団体の相談窓口 – 中立的な情報提供
NISA制度に関する一般的な情報提供や、基本的な疑問に応えることを目的とした公的機関や関連団体の相談窓口もあります。
メリット
- 無料で利用できる場合が多い
多くの場合、無料で相談に応じてくれます。 - NISA制度に関する基本的な情報を得られる
特定の金融機関や商品に偏らない、中立的な立場でNISA制度の仕組みや概要について教えてもらえます。 - 信頼性が高い情報源
金融庁や日本証券業協会などが提供する情報は信頼性が高いと言えます。
金融庁「NISA特設ウェブサイト」:https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/index.html
日本証券業協会「NISA相談コールセンター」: https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/tax/callcenter.html
デメリット
- 具体的な金融商品の推奨や個別プランの提案は行わない
これらの窓口は、あくまで制度の啓発や一般的な情報提供が主目的であるため、「どの商品が良いか」「あなたの場合はどうすべきか」といった個別具体的なアドバイスや商品の推奨は行われません。
「ネット証券での資産運用を相談したい!」そんな方へ

私たち「投資信託相談プラザ」はSBI証券・楽天証券と提携しており、仲介口座数は延べ60,000口座、仲介する預かり資産残高は4,500億円超の実績があります。(※)
全国各地の店舗・またはオンラインで無料相談できます。お気軽にご利用ください!
※令和7年12月時点
\ SBI証券・楽天証券 提携窓口 /
お金にまつわる相談をしたい、知識を得たいなら?
その他のお金にまつわる相談をしたい、お金にまつわる知識を習得したいなら、こういった選択肢も検討できます。
- FP(ファイナンシャル・プランナー)に相談する
- 税理士に相談する
- 大学の公開講座などを受講する
FP(ファイナンシャル・プランナー)
FPは、個人のライフプラン(人生設計)に基づいて、資金計画やアドバイスを行う専門家です。FPの相談範囲は、資金計画だけでなく、保険、不動産、住宅ローン、年金、税金、相続など、お金に関する幅広い分野に及びます。ライフプラン全体の改善を目的としたアドバイスが中心です。
税理士
相続や贈与、不動産の売買など、税金に関わるお金の相談であれば、税理士に相談しましょう。節税対策や確定申告についても相談できます。
大学の公開講座などを受講する
特に近年は「金融リテラシー」や「資産形成」といったテーマの関心の高まりから、公開講座を開講している大学が増えています。公的機関が協力し講師を派遣しているケースもあります。地域住民や社会人を対象としたプログラムであれば、自分の知識に自信がないという方でも気軽に受講することができるでしょう。
自分のニーズに合った相談窓口を見つける!選び方のポイント
ここまで様々な相談窓口を見てきましたが、「結局どこに相談すればいいの?」と迷う方もいらっしゃるでしょう。 ここでは、ご自身に合った相談窓口を選ぶためのポイントをご紹介します。
1. 相談したい内容を明確にする(制度の基本?商品選び?運用戦略?)
まず、自分がNISAに関して「何を知りたいのか」「何を相談したいのか」を具体的にすることが大切です。
- 「NISA制度の基本的な仕組みやメリット・デメリットを知りたい」という段階であれば、金融機関の窓口や公的機関の相談窓口でも十分な情報を得られる可能性があります。
- 「自分に合った金融商品は何か、具体的な選び方を教えてほしい」という場合は、幅広い商品知識や品ぞろえの多い証券会社やIFAなどが適しているかもしれません。
相談内容が明確であればあるほど、適した相談先を選びやすくなります。まずは、実際にいくつかの相談窓口で話を聞いてみるのもよいでしょう。
なお、弊社「株式会社Fan」が運営する「投資信託相談プラザ」では、資産運用アドバイスのプロであるIFAが、NISAを活用した資産運用をサポートしております。
全国に17店舗展開しているため対面でご相談できるほか、オンラインでもご相談可能です。
- ネット証券の口座を開設したけれど、銘柄選びなどその後の進め方がわからない
- 専門用語が多くて挫折してしまった
このような方でも、ぜひお気軽にご利用ください。
「投資信託相談プラザ」でNISA相談いただく場合に、事前準備をおすすめしている3つのこと
1. 現在の収入・支出・資産状況を整理しておく
より具体的なアドバイスを受けるためには、ご自身の経済状況を正確に伝えることが重要です。
- 毎月の収入と支出
家計簿をつけている場合は持参すると良いでしょう。大まかな収支バランスを把握しておくだけでも役立ちます。 - 現在の預貯金、他の投資状況など
どれくらいの資産があり、他にどのような運用をしているか(あるいはしていないか)を伝えることで、NISAでどれくらいの金額を運用するのが適切か、といったアドバイスを受けやすくなります。 - 借入金(住宅ローンなど)の状況
負債の状況もライフプランニングにおいて重要な要素です。
これらの情報を事前にまとめておくことで、相談がスムーズに進み、より的確なアドバイスにつながるでしょう。
2. 将来のライフプランや資産運用の目的・目標額を考えておく
NISAを何のために活用したいのか、将来どのような生活を送りたいのか、といった目的や目標を明確にしておきましょう。
- 資産運用の目的
「老後資金のため」「子どもの教育資金のため」「住宅購入の頭金のため」など、具体的な目的を伝えることで、それに合った運用期間やリスク許容度、目標金額の目安が見えてきます。 - いつまでに、いくらくらい準備したいか
具体的な時期や金額の目標があれば、より計画的な運用プランを立てるのに役立ちます。漠然としていても構いませんので、現時点でのイメージを伝えてみましょう。 - リスクに対する考え方
どの程度のリスクなら許容できるか、あるいはできるだけリスクを抑えたいかなど、ご自身の考えを伝えておくことも大切です。
これらの情報は、相談相手があなたにプランを提案する上で非常に重要な手がかりとなります。
3. NISAに関する基本的な疑問点や聞いてみたいことをリストアップしておく
相談時間が限られている場合もあるため、事前に聞きたいことを整理しておくと効率的です。
- NISA制度について分からないこと
例えば、「つみたて投資枠と成長投資枠の使い分けはどうすればいい?」など、制度に関する疑問点をまとめておきましょう。 - 金融商品について聞きたいこと
「投資信託ってそもそも何?」「株との違いは?」「どんな種類があるの?」など、商品に関する基本的な質問も遠慮なく準備しておきましょう。 - 運用方法や注意点について知りたいこと
「積立頻度はどうすればいい?」「運用中に気をつけることは?」「途中で引き出すことはできる?」など、具体的な運用に関する疑問もリストアップしておくと良いでしょう。
メモ書き程度でも構いませんので、事前に質問事項を準備しておくことで、聞き忘れを防ぎ、相談時間を有効に活用できます。
あわせて読みたい
※NISAのご注意事項
・配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISA口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
・同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
・NISAで購入できる商品は金融商品取引業者が指定する商品に限られます。
・2024年からのNISAでは年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
・損失は税務上ないものとされます。
・出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
・2024年からのNISAにおけるつみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
・その他、2024年からのNISAに関するご注意事項、並びに2023年までの一般NISA ・つみたてNISA等に関するご注意事項の詳細は金融商品取引業者のWEBサイトにてご確認ください。
このコラムの執筆者

道谷 昌弘
株式会社Fan IFA
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

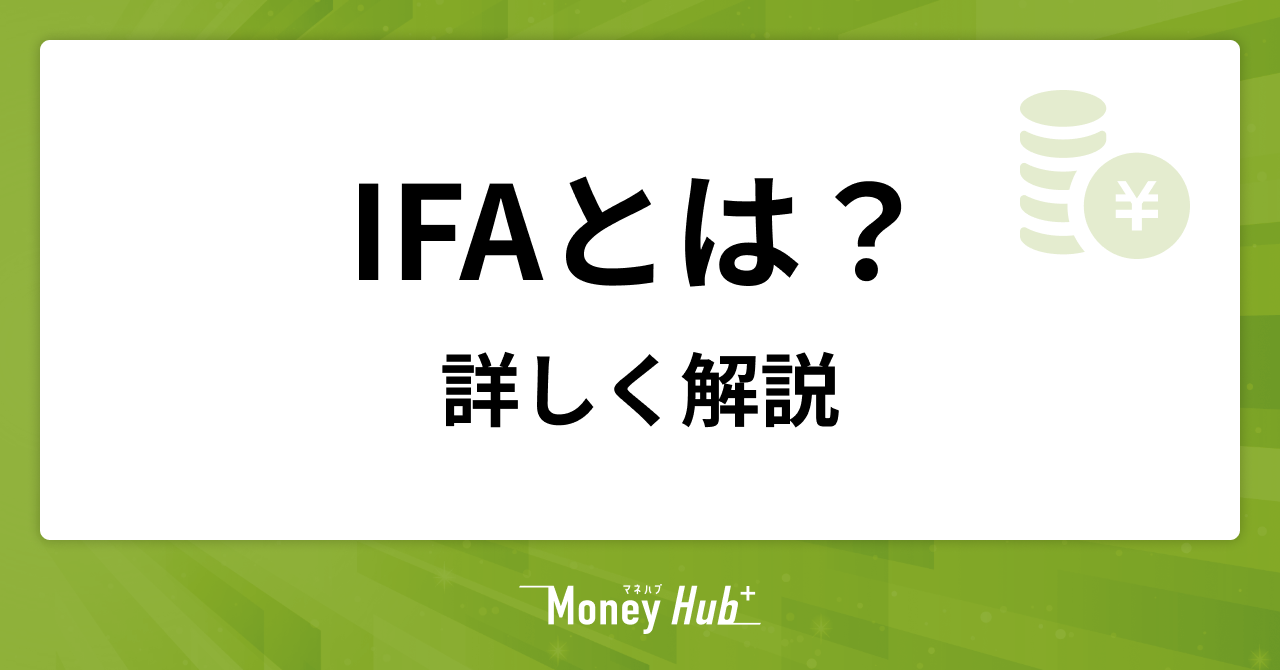

































































AFP(日本FP協会認定) 大学卒業後、大手証券会社に入社。国内営業部門にて法人・個人の資産運用アドバイスを行う。8年間勤めたのち退社し、より中立的なアドバイスができるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。現在は富山を拠点に、全国各地のお客様に幅広くコンサルティングを行いながら、お客様にとって本当に良い商品提案を日々追求している。