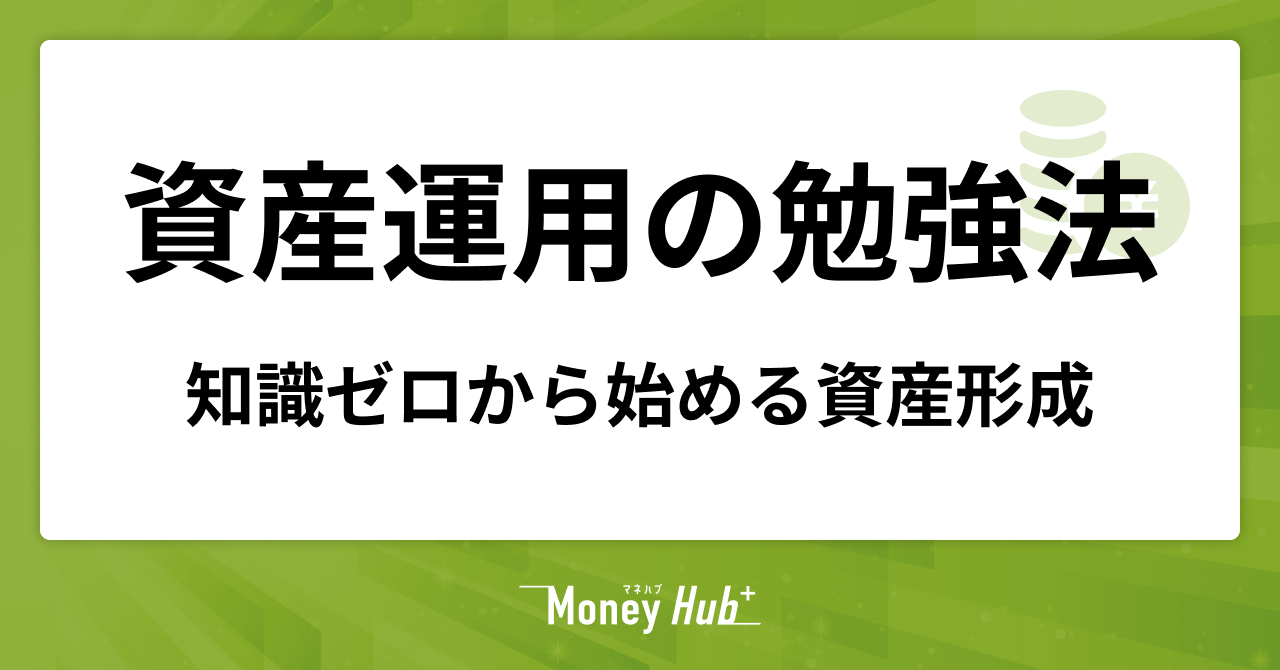
この記事のポイント
- なぜ資産運用の勉強が必要か:低金利やインフレから資産の価値を守るため
- ①目的設定 → ②基本原則の理解 → ③商品理解 → ④制度活用 → ⑤少額実践 の流れで勉強を進めよう
- 勉強の方法:本、Web、資格、セミナーなど自分に合った方法を選ぶ
「将来のために資産運用を始めたいけど、何から勉強すればいいか分からない…」
「本やネットを見ても情報が多すぎて、頭に入ってこない…」
将来のお金に対する漠然とした不安から資産運用の必要性を感じつつも、知識不足から一歩を踏み出せずにいる方は非常に多いのではないでしょうか。
しかし、ご安心ください。正しい順序でステップを踏んでいくことによって、誰でも無理なく学んでいくことができます。
この記事では、IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)の視点から、資産運用の勉強を始めたいと考えているあなたのために、以下の点を分かりやすく解説します。
- なぜ今、資産運用の勉強が必要なのか
- 初心者が陥りがちな勉強の落とし穴
- 知識ゼロから始めるための具体的な5ステップ・ロードマップ
- あなたに合った勉強法の選び方
この記事を最後まで読めば、資産運用の全体像が明確になり、「まず何をすべきか」が具体的にわかります。ぜひ、 資産運用への第一歩を一緒に踏み出しましょう。
「これから資産運用を始めたい!」そんな方へ

資産運用の基本や運用のコツ、活用したい制度や実践方法など、資産運用の基礎をまるごと学べるハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
INDEX
なぜ今、多くの人が資産運用の勉強を始めているのか?
近年、「資産運用」という言葉を耳にする機会が急激に増えました。なぜ今、これほどまでに資産運用の必要性が叫ばれているのでしょうか。その背景には、私たちの生活に直結する3つの経済的な変化があります。
理由1:銀行預金だけではお金が増えない「低金利時代」
かつて日本の銀行預金の金利は高く、郵便局にお金を預けておくだけで、10年で倍になる時代もありました。しかし、現在の超低金利時代では、大手銀行の普通預金金利は年0.2%程度。100万円を1年間預けても、利息はわずか2,000円(税引前)です。
出典:円預金金利 | 三菱UFJ銀行(2025年8月8日時点)
これでは、いくら地道に貯金をしても、お金そのものが増えることはあまり期待できません。自分の資産を自分で育てていく必要性が高まっているのです。
理由2:お金の価値が下がる「インフレ」への備え
インフレ(インフレーション)とは、モノやサービスの値段が上がり、相対的にお金の価値が下がることです。例えば、今まで100円で買えていたジュースが120円に値上がりした場合、同じ100円で買えるものが少なくなってしまうため、お金の価値は実質的に目減りしてしまいます。
総務省統計局が発表する消費者物価指数を見ると、近年、私たちの身の回りのモノやサービスの価格が上昇傾向にあることがわかります。
参考:総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)7月分」
預金金利がインフレ率を下回っている場合、銀行に預けているお金は、数字の上では減っていなくても、実質的な価値はどんどん下がっていってしまうのです。このインフレから資産価値を守るためにも、資産運用は有効な手段となります。
理由3:国も後押しする「貯蓄から投資へ」の流れ
こうした社会情勢の変化を受け、政府も国民の安定的な資産形成を後押しするために「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げています。その代表的な施策が、2024年1月から新しくなったNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)です。
NISAは、個人の資産運用を税制面で優遇する制度であり、国が「国民一人ひとりが、自分自身で資産形成に取り組むことを期待している」というメッセージの表れとも言えます。
参考:金融庁「NISA特設ウェブサイト」
「資産運用を体系的に学びたい!」そんな方へ

私たち「投資信託相談プラザ」は、毎月全国各地・オンラインにて資産運用セミナーを開催しています。(参加費無料)
参加者数は延べ70,000人超(※)。ぜひお気軽にご参加ください!
※2015年12月~2025年7月末までの実績
\ SBI証券 共催・楽天証券 協賛 /
【要注意】初心者が勉強で陥りがちな3つの落とし穴
資産運用の勉強を始めようという意欲は素晴らしいですが、やる気を空回りさせないためにも、初心者が陥りがちな失敗パターンを知っておきましょう。
落とし穴1:いきなり個別株やFXなど価格変動が大きいものに手を出す
FXは、少ない資金で大きな取引ができる「レバレッジ」があることや、為替相場の予測が難しいこと、為替相場に影響を与える要因が多岐にわたることなどの理由から、また、株式は企業固有の要因、市況等により、投資元本を下回り、大きな損失を被るリスクがあります。
まずは、よりリスクを抑えやすい商品から始めるのが賢明です。
落とし穴2:SNSやネットの情報を鵜呑みにしてしまう
SNS上には「絶対に儲かる」「この銘柄がおすすめ」といった魅力的な情報が溢れています。
しかし、その中には根拠のない情報や、詐欺的な勧誘も少なくありません。誰が発信しているのか分からない情報を鵜呑みにするのではなく、公的機関や信頼できる金融機関の発信する情報をもとに、自分で判断する力を養うことが重要です。
落とし穴3:目的や目標がないまま始めてしまう
「なんとなく不安だから」というだけで資産運用を始めると、価格が少し下がっただけで不安になって売ってしまったり、逆に少し利益が出ただけですぐにやめてしまったりと、長期的な視点での運用が難しくなります。
「何のために(目的)、いつまでに(期間)、いくら増やしたいのか(目標額)」というゴールを定めることで、取るべきリスクや選ぶべき商品が明確になり、一貫した運用が可能になります。
知識ゼロから始める!資産運用の勉強5ステップ・ロードマップ
では、具体的に何からどのように勉強を進めればよいのでしょうか。ここでは、初心者の方が着実に知識を身につけるための5つのステップをご紹介します。
ステップ1:【目的の明確化】なぜ資産運用をするのかを考える
最初のステップは、あなた自身の「資産運用の目的」を明確にすることです。
- 老後資金:65歳までに2,000万円を準備したい
- 教育資金:15年後に子供の大学費用として500万円を用意したい
- 住宅購入:10年後に頭金として300万円を作りたい
このように目的を具体的にすることで、必要な利回りや許容できるリスクの度合いが見えてきます。このステップが、あなたの資産運用における羅針盤となります。
ステップ2:【基本原則の理解】「長期・積立・分散投資」を学ぶ
資産運用の世界には、リスクを抑えながら安定的な成果を目指すための基本原則があります。それが「長期・積立・分散」の3つです。
- 長期投資:短期的な価格の変動に一喜一憂せず、長い時間をかけて資産が成長するのを待つ考え方。
- 積立投資:毎月1万円など、決まった金額を定期的に買い続ける方法。価格が高いときには少なく、安いときには多く買うことができるため、平均購入単価を抑える効果(ドルコスト平均法)が期待できます。
- 分散投資:一つの商品に集中投資するのではなく、値動きの異なる複数の資産(国・地域、資産の種類など)に分けて投資すること。これにより、一つの資産が値下がりしても、他の資産でカバーできる可能性が高まります。
この3つの原則は、特に投資初心者にとって非常に重要な考え方です。
ステップ3:【金融商品の把握】主な投資の種類と特徴を知る
世の中には様々な金融商品がありますが、まずは代表的なものの特徴をざっくりと理解しましょう。
| 金融商品 | 特徴 | リスク・リターン |
|---|---|---|
| 債券 | 国や企業がお金を借りるために発行する有価証券。償還まで保有すれば、定期的に利子を受け取り、償還日には元本が戻ってくる。(発行体の信用リスクはあります) | ローリスク・ローリターン |
| 投資信託 | 投資家から集めた資金を専門家(ファンドマネージャー)が国内外の株式や債券などに分散投資してくれる商品。初心者でも少額から比較的容易に始められるのが魅力。 | ミドルリスク・ミドルリターン |
| 不動産(REIT) | 多くの投資家から集めた資金で不動産を購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品。少額から不動産投資ができる。 | ミドルリスク・ミドルリターン |
| 株式 | 企業が発行する株式を買い、株主になること。株価の値上がり益(キャピタルゲイン)や配当金(インカムゲイン)が期待できる。 | ハイリスク・ハイリターン |
✅ 初心者は、まず投資信託から始めるのがおすすめです。
投資信託には株式や債券、不動産などを組み合わせて作っているパッケージ商品もあるため自然と分散投資ができ、リスクの軽減につながります。また、少額から始められるため、資産運用の第一歩として検討する良い選択肢と言えるでしょう。
ステップ4:【資産形成におすすめな制度の活用】NISAとiDeCoを理解する
資産運用を行う上で、ぜひ活用したいのが税金が優遇される制度です。代表的なものが「NISA」と「iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)」です。
- NISA:2つの投資枠合計で、年間最大360万円までの投資で得られた利益が非課税になる制度。いつでも引き出し可能で自由度が高い。
- iDeCo:原則60歳まで引き出せない私的年金制度。掛金が全額所得控除の対象になり、運用益も非課税になるなど、税制優遇が非常に大きい。
これらの制度をうまく活用することで、より効率的に資産を増やすことが可能になります。まずはNISAから理解を深めていくのがよいでしょう。
あわせて読みたい
「NISAを使って資産運用を始めたい!」そんな方へ
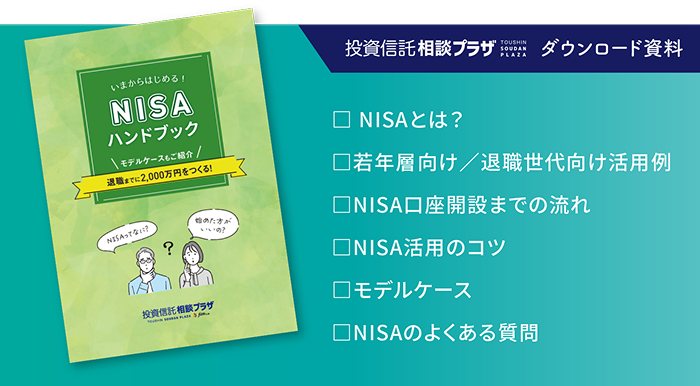
NISA(少額投資非課税制度)のしくみや活用のコツ、実際の活用例などをまとめたハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
ステップ5:【実践】まずは「少額」から始めてみる
ある程度の知識が身についたら、最後は実践です。まずは月々5,000円や1万円といった、生活への影響が少ない「少額」から始めてみましょう。
実際に自分のお金で運用してみることで、経済ニュースへの感度が高まったり、値動きを肌で感じたりと、本を読むだけでは得られない多くの学びがあります。
少額投資は、机上の知識を実践的な経験へと変えるための、とても効果的な学習法です。
【方法別】あなたに合った資産運用の勉強法5選
ロードマップが理解できたら、次は具体的な勉強方法です。ここでは5つの方法をご紹介しますので、ご自身のライフスタイルや好みに合わせて組み合わせてみてください。
1. 本で体系的に学ぶ
資産運用の知識を断片的にではなく、体系的に学びたい場合は、本を読むのがよいでしょう。まずは、初心者向けに書かれた広く読まれている本を2〜3冊ほど読んでみることから始めてみましょう。多くの人に読まれている本は、それだけ分かりやすく、資産運用の全体像を掴むのに役立ちます。
【重要】ただし、本の内容の鵜呑みは厳禁です
投資の世界に「唯一の正解」はありません。著者によって考え方や推奨する手法は異なります。一冊の本を信じ込むのではなく、複数の本を読み比べ、異なる視点に触れることが非常に重要です。
そのうえで、自分自身の考え方やリスク許容度に合った方法は何かを吟味し、情報を見極めていく姿勢を持ちましょう。
2. Webサイトや動画で手軽に学ぶ|信頼できる情報源
通勤時間や家事の合間など、スキマ時間を使って手軽に学びたい方には、WebサイトやYouTubeがおすすめです。ただし、情報の信頼性には注意が必要です。
- 金融庁のWebサイト:NISAやiDeCoの公式情報や、資産形成に関する基本的な資料が豊富です。金融庁 Webサイト
- 日本証券業協会のウェブサイト:「投資の時間」など、初心者向けのコンテンツが充実しています。日本証券業協会 Webサイト
- 信頼できる金融機関のコラムやYouTubeチャンネル:
大手証券会社や銀行が発信する情報は、信頼性が高く参考になります。
3. 資格(FPなど)の勉強で知識を深める
より深く、網羅的に知識を身につけたいという意欲のある方は、FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格取得を目指すのもよいでしょう。金融、税制、不動産、相続など、お金に関する幅広い知識が身につき、自分自身の資産運用にも大いに役立ちます。
参考:日本FP協会
4. 証券会社の提供する情報・ツールを活用する
ネット証券の口座を開設すると、無料で利用できる学習コンテンツやレポート、資産配分をシミュレーションできるツールなどが数多く提供されています。これらを活用することをおすすめします。口座開設は無料なので、情報収集のために複数の証券会社に口座を持つのも一つの手です。
5. セミナーに参加してプロから直接学ぶ
本やネットでの独学には、どうしても限界があります。 「自分の場合はどうなんだろう?」 「この解釈で合っているのかな?」 といった個別の疑問や不安は、なかなか解消しにくいものです。
そんな時におすすめなのが、資産運用のセミナーに参加してみることです。セミナーでは、金融の専門家から直接、最新の情報を交えながら体系的に学ぶことができます。また、質疑応答の時間を通じて、自分の疑問をその場で解消できるのは大きなメリットです。
「資産運用を体系的に学びたい!」そんな方へ

私たち「投資信託相談プラザ」は、毎月全国各地・オンラインにて資産運用セミナーを開催しています。(参加費無料)
参加者数は延べ70,000人超(※)。ぜひお気軽にご参加ください!
※2015年12月~2025年7月末までの実績
\ SBI証券 共催・楽天証券 協賛 /
資産運用の勉強に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 勉強にはどれくらいの時間がかかりますか?
A1. 一概には言えませんが、まずは1ヶ月程度を目標に、本を1〜2冊読み、基本的な用語や制度(NISAなど)を理解することから始めてみましょう。大切なのは、完璧を目指すことではなく、学びながら実践し、実践しながら学び続けることです。
Q2. 勉強してからでないと、投資は始められませんか?
A2. いいえ、そんなことはありません。先述の通り、少額から実践してみること自体が勉強になります。基本的な知識(長期・積立・分散、NISA、投資信託)をインプットしたら、月々数千円からでも積立投資を始めてみることを強くおすすめします。
Q3. 独学だけで資産運用を始めても大丈夫ですか?
A3. 独学でも資産運用を始めることは可能です。しかし、金融の世界は情報が常にアップデートされており、一人で全てを正しく理解し続けるのは簡単ではありません。
間違った判断で大切な資産を失うリスクを避けるためにも、時には資産運用アドバイスの専門家の視点を取り入れることが、結果的に成功への近道となる場合があります。
まとめ:正しい知識は、将来の資産を守るための強力な味方
今回は、資産運用の勉強を何から始めるべきか、その具体的なロードマップと勉強法について解説しました。
- なぜ勉強が必要か:低金利やインフレから資産の価値を守るため
- 勉強のロードマップ:①目的設定 → ②基本原則 → ③商品理解 → ④制度活用 → ⑤少額実践
- 勉強の方法:本、Web、資格、セミナーなど自分に合った方法を選ぶ
資産運用の勉強は、過度に難しく考える必要はありません。正しい手順で一歩ずつ進めば、着実に知識は身につきます。そして、身につけた知識は、これからの長い人生において、あなたの大切な資産を守り、育てるための強力な味方となるでしょう。
もし、この記事を読んで「独学だけでは少し不安…」「自分の状況に合ったアドバイスが欲しい」と感じたなら、一度専門家に相談してみるのも有効な選択肢です。
私たち「投資信託相談プラザ」では、特定の金融機関に属さない中立的な立場のIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)が、初心者の方にも分かりやすく資産運用の基本をお伝えする無料セミナーを定期的に開催しています。全国各地の会場、およびオンラインでのご参加が可能です。
無理な勧誘はいたしませんので、まずは情報収集の場として、お気軽にご参加ください。あなたの資産運用に関する疑問や不安を、専門家が丁寧に解消するお手伝いをいたします。
「これから資産運用を始めたい!」そんな方へ

資産運用の基本や運用のコツ、活用したい制度や実践方法など、資産運用の基礎をまるごと学べるハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
このコラムの執筆者

道谷 昌弘
株式会社Fan IFA
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

































































AFP(日本FP協会認定) 大学卒業後、大手証券会社に入社。国内営業部門にて法人・個人の資産運用アドバイスを行う。8年間勤めたのち退社し、より中立的なアドバイスができるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。現在は富山を拠点に、全国各地のお客様に幅広くコンサルティングを行いながら、お客様にとって本当に良い商品提案を日々追求している。