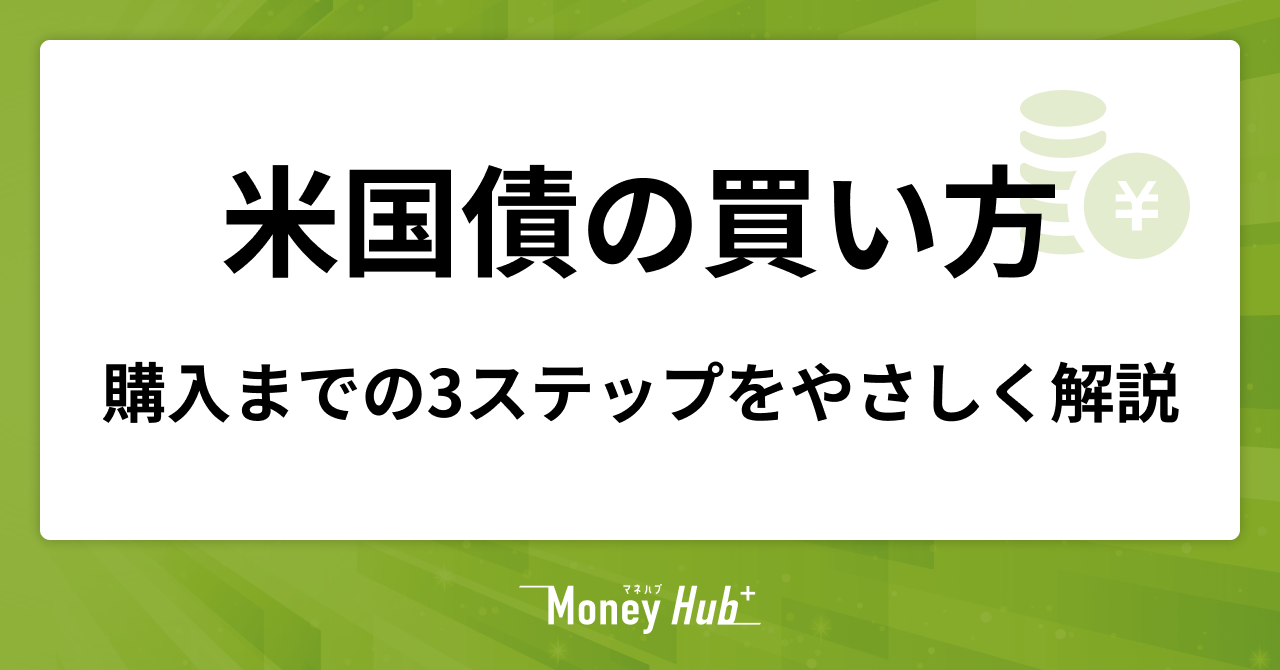
「将来のために資産運用を始めたいけど、株は値動きが激しくて少し怖い…」
「円安が進む中で、日本円だけで資産を持っているのは不安…」
昨今の経済状況から、このように考える方が増えています。そんな中、資産運用の選択肢として、流動性が高く換金が容易で、相対的に信用力が高いとされる「米国債」への関心が高まっています。
米国債は、アメリカ合衆国が発行する債券です。国が発行体であるため、一般的に企業が発行する社債などに比べて信用度が非常に高い資産と言われています。
しかし、いざ米国債を買おうと思っても、
- 「そもそも、どこでどうやって買えばいいの?」
- 「ドルで買うって難しそう…」
といった疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな投資初心者の方に向けて、米国債の買い方をゼロから分かりやすく解説します。米国債投資のメリット・デメリットといった基本から、口座開設、具体的な購入手順といった実践的なステップまで、この記事一本でゼロから理解できるように構成しました。
資産形成の第一歩を、ここから踏み出しましょう。
「債券投資に興味がある!」そんな方へ
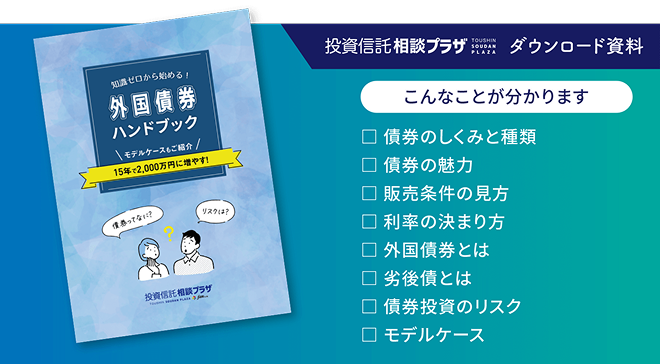
債券のしくみや魅力、実際の活用例などをまとめたハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
INDEX
米国債投資の基本|3つのメリットと2つのデメリット
まずは、米国債に投資する上で必ず押さえておきたい基本的なメリットとデメリット(リスク)を見ていきましょう。
メリット1:高い信用力と安定性
米国債のメリットは、その発行体であるアメリカ合衆国の高い信用力です。世界経済の中心である米国の国債は、デフォルト(債務不履行)に陥るリスクが極めて低いと考えられています。
そのため、金融の世界では「安全資産」の代表格として扱われています。
参考:「PRI Open Campus なぜ米国債はグローバルな 安全資産なのか」(財務総合政策研究所 主任研究官 松岡 秀明)
メリット2:定期的な利子収入(インカムゲイン)
一般的な米国債である「利付債」を購入すると、保有している間、定期的に利子(クーポン)を受け取ることができます。銀行預金の金利が非常に低い現在、米国債の金利は魅力的な選択肢の一つとなり得ます。
この安定したインカムゲインは、計画的な資産形成の土台となります。
メリット3:米ドルで資産を保有できる
米国債は米ドル建てで取引されるため、購入するということは実質的に米ドルで資産を持つことを意味します。近年のような円安局面では、円の価値が下がる一方でドルの価値が上がるため、ドル建て資産を持っていることで為替差益を得られる可能性があります。
資産を円だけでなくドルにも分散させることで、円資産の価値減少への備えになります。
デメリット1:為替変動リスク
米ドルで資産を持つことの裏返しとして、為替変動リスクは避けられません。購入時よりも円高(例:1ドル150円→130円)が進むと、利子や償還時に受け取るドルを円に換金する際に、為替差損が発生してしまいます。
デメリット2:金利変動リスク
債券の価格は、市場の金利と密接な関係にあります。一般的に、市場の金利が上昇すると、既に発行されている債券の価格は下落します。
これは、新しく発行される債券の方が金利が高く魅力的になるため、相対的に既存の債券の人気が下がるからです。償還まで保有すれば額面金額が戻ってきますが、途中で売却する場合には、購入時よりも価格が下落している(元本割れ)可能性がある点に注意が必要です。
あわせて読みたい
「外国債券投資について相談したい!」そんな方へ

私たち「投資信託相談プラザ」はSBI証券・楽天証券と提携しており、仲介口座数は延べ58,000口座(※)、仲介する預かり資産残高は4,000億円(※)を超えています。
全国各地の店舗・またはオンラインで無料相談可能です。お気軽にご利用ください!
※令和7年7月時点
【米国債を購入するための3ステップ】米国債の買い方・購入方法の全体像
米国債の購入は、実はそれほど難しいものではありません。大まかな流れは以下の3ステップです。
- STEP1:米国債を購入する金融機関を選ぶ
- STEP2:証券総合口座と外国証券取引口座を開設する
- STEP3:米国債を選んで買い注文を出す
一つずつ、詳しく見ていきましょう。
STEP1:米国債を購入する金融機関を選ぶ
米国債は、主に証券会社や銀行で購入することができます。それぞれの特徴を比較して、自分に合った金融機関を選びましょう。
あわせて読みたい
STEP2:証券総合口座と外国証券取引口座を開設する
購入する金融機関を決めたら、次は口座開設です。ここでは、ネット証券を例に解説します。
✅️ 口座開設に必要なものリスト
スムーズに手続きを進めるために、あらかじめ以下の3点を準備しておきましょう。
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 銀行口座情報(出金先として登録する口座)
✅️ 口座開設の基本的な流れ(3ステップ)
- オンラインで申し込み
証券会社の公式サイトにアクセスし、氏名・住所などの必要情報を入力します。 - 本人確認
最近では、スマートフォンで本人確認書類と自分の顔を撮影するだけで完結する「スマホでかんたん本人確認」が主流です。郵送での手続きも選択できます。 - 審査・口座開設完了
証券会社による審査が行われ、完了するとID・パスワードが発行され、取引を開始できます。
✅️ 外国証券取引口座の開設と購入資金の入金方法
米国債を購入するには、通常の証券総合口座に加えて「外国証券取引口座」の開設が必要です。多くの場合、証券総合口座の開設と同時に申し込むことができます。
口座が開設できたら、購入資金を入金します。一般的な流れは、まず証券口座に日本円で入金し、その資金を米ドルに両替(為替振替)してから米国債を購入します。
この両替の際には、「為替手数料(スプレッド)」というコストがかかることを覚えておきましょう。
STEP3:米国債を選んで買い注文を出す
いよいよ、最後のステップです。
✅️ ネット証券での米国債の買い方
ここでは、一般的なネット証券の取引画面をイメージしながら、購入手順を解説します。
- 証券口座にログインし、「外国債券」メニューを選択
まずは証券会社のウェブサイトにログインします。トップページやメニュー一覧から「債券」や「外国債券」といった項目を探してクリックします。 - 取扱銘柄一覧から購入したい米国債を探す
現在購入できる米国債の一覧が表示されます。「利回り」「償還日(償還までの期間)」などの条件で絞り込みながら、自分の希望に合った銘柄を探しましょう。 - 契約締結前交付書面等や商品説明資料等を確認
購入したい銘柄が見つかったら、必ず「契約締結前交付書面等」や商品説明資料に目を通しましょう。リスクに関する重要な情報も含まれているため、必ず確認する癖をつけましょう。 - 注文画面で「購入数量」などを入力し、注文を確定する
内容を理解したら、注文画面に進みます。購入したい金額(数量)を入力し、注文内容の確認画面で最終チェックを行い、問題がなければ注文を確定します。
これで、米国債の購入手続きは完了です。
米国債に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 米国債はいくらから買えますか?
A. 金融機関や銘柄によりますが、ネット証券では最低購入金額が100米ドル程度から設定されていることが多いです。
日本円で数万円程度から始められるため、少額から試してみたいという方にもおすすめです。
Q2. NISA(成長投資枠)を使って米国債は買えますか?
A. いいえ、残念ながら2025年現在、NISA制度で個別の米国債を購入することはできません。
NISAの対象は、主に株式や投資信託などに限定されています。ただし、米国債を投資対象とする投資信託であれば、NISAの対象になる場合があります。
Q3. 償還まで待たずに売却できますか?
A. はい、原則として償還前に市場価格で売却(中途売却)することが可能です。
ただし、その時の金利動向や市場の状況によって価格は変動するため、購入価格を上回ることもあれば、下回って元本割れする可能性もあります。
あわせて読みたい
まとめ:自分に合った米国債の買い方がわからない…そんな時はIFAへの相談も検討しよう
この記事では、米国債の買い方について、口座開設から具体的な購入手順を網羅的に解説しました。一連の流れはご理解いただけたかと思います。
一方で、
- 「たくさんの銘柄の中から、どのくらいの『利回り』や『償還日』の米国債を選べば、自分の目的に合うのだろう?」
- 「NISAでは個別債券は買えないけど、『米国債を投資対象とする投資信託』なら対象になる場合があるって本当?自分はどちらを選ぶべきなんだろう?」
- 「解説にあった『為替変動リスク』や『金利変動リスク』を考えると、どのタイミングで購入するのがベストなのだろう?また、これらのリスクを少しでも抑える具体的な方法はあるのだろうか?」
といった、より一人ひとりの状況に合わせたパーソナルな疑問も湧いてきたのではないでしょうか。
本やインターネットで得られる知識には限界があり、なかなか、自分のライフプランに合わせた金融商品の選び方まではわからないという人が多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みは、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談するのがおすすめです。(IFAとは?)
弊社が運営する「投資信託相談プラザ」では、経験豊富なIFAが、中立的な立場で、お客様一人ひとりの資産状況やライフプランに合わせた運用方法をご提案します。米国債に関するご相談はもちろん、お客様の資産全体のバランスを見た上でのアドバイスが可能です。
「まずは基本的なことから聞いてみたい」「自分の考えが合っているか確認したい」といった動機でも構いません。まずは無料相談で、あなたのお悩みをお聞かせください。
「外国債券投資について相談したい!」そんな方へ

私たち「投資信託相談プラザ」はSBI証券・楽天証券と提携しており、仲介口座数は延べ58,000口座(※)、仲介する預かり資産残高は4,000億円(※)を超えています。
全国各地の店舗・またはオンラインで無料相談可能です。お気軽にご利用ください!
※令和7年7月時点
「債券投資に興味がある!」そんな方へ
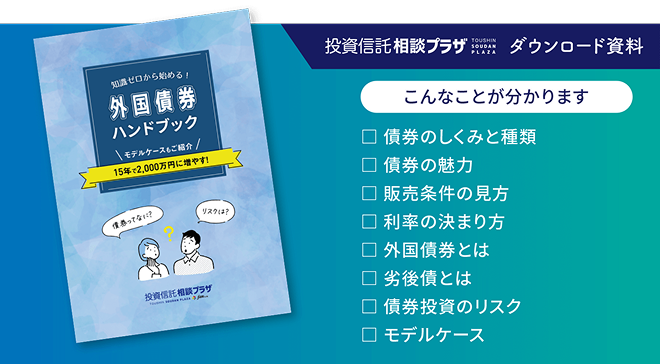
債券のしくみや魅力、実際の活用例などをまとめたハンドブックをご用意しました。
無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください!
【国内債券のリスクと費用について】
国内債券の取引にかかるリスク:債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。
国内債券の取引にかかる費用:国内債券を、相対取引によって購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。
【外国債券のリスクと費用について】
外国債券の取引にかかるリスク : 債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。
外国債券の取引にかかる費用等 : 外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。
このコラムの執筆者

道谷 昌弘
株式会社Fan IFA
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

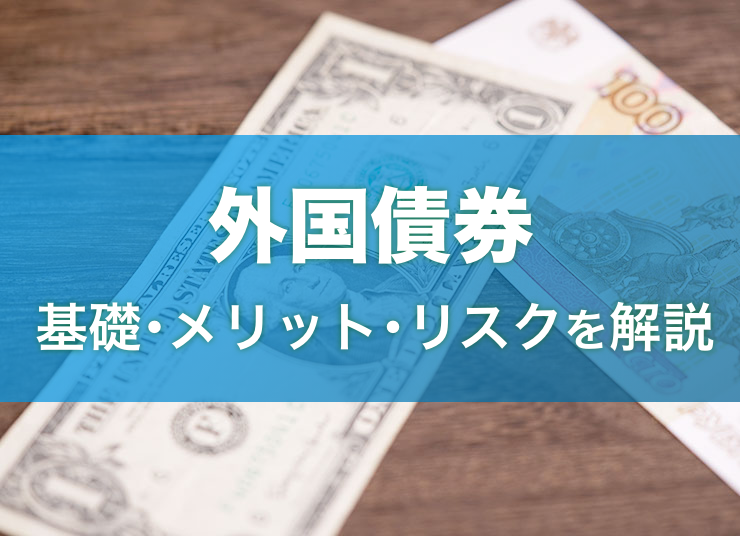

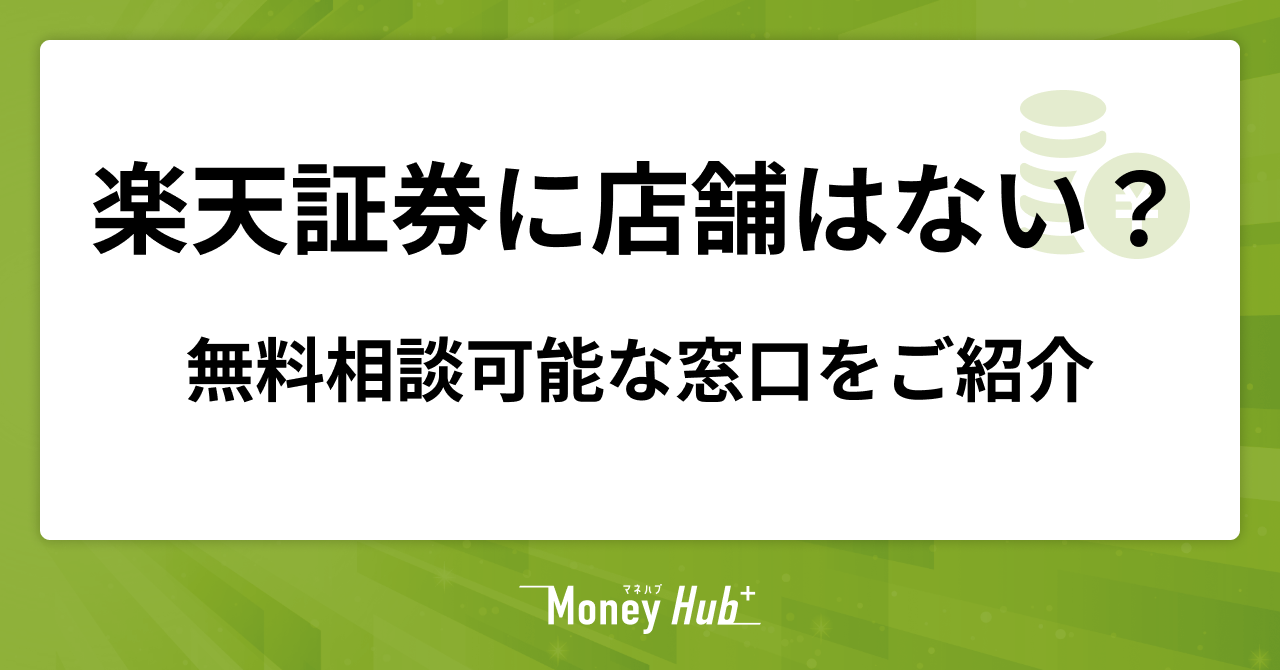































































AFP(日本FP協会認定) 大学卒業後、大手証券会社に入社。国内営業部門にて法人・個人の資産運用アドバイスを行う。8年間勤めたのち退社し、より中立的なアドバイスができるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。現在は富山を拠点に、全国各地のお客様に幅広くコンサルティングを行いながら、お客様にとって本当に良い商品提案を日々追求している。