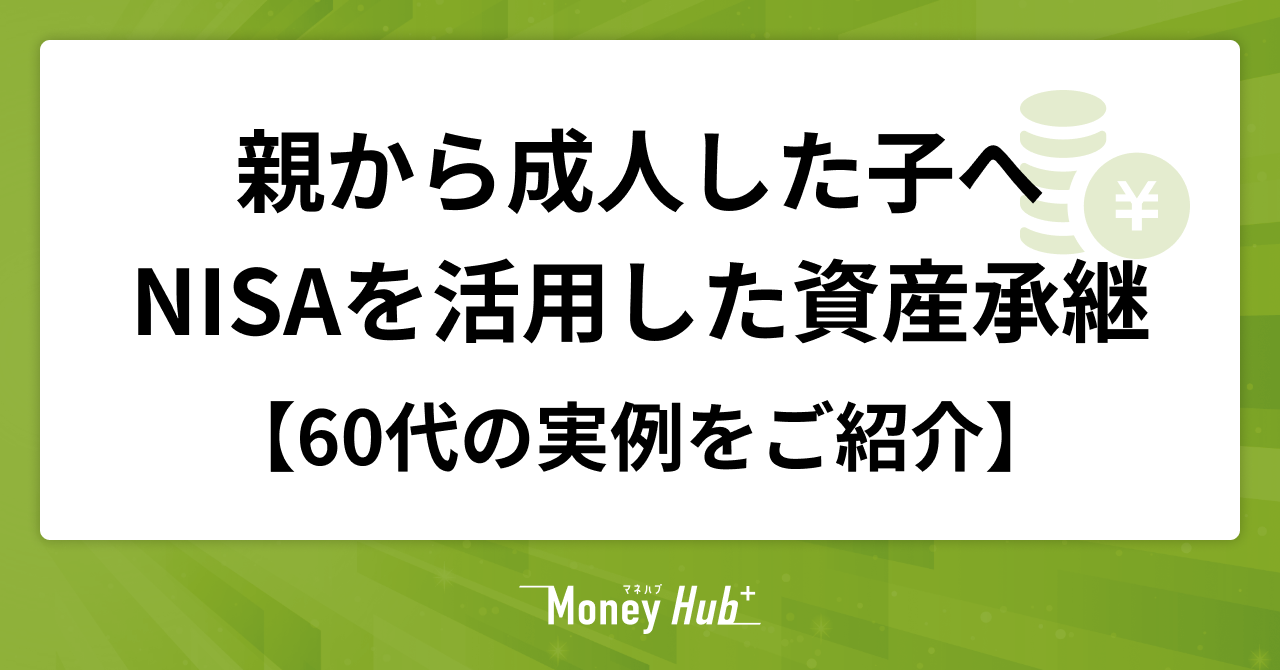
この記事のポイント
- NISAは運用益・配当金・分配金が非課税となるため、長期的な複利効果を最大限に活かした、時間を味方につけた資産形成が可能
- 子どものライフステージに合わせて、自由に運用を続けることができる
- 単なる資金援助ではなく、子どもが自ら考え投資判断を行うことで、金融リテラシーを身につけ、実践的な資産形成力を育むことができる
「子どもたちが成人して、NISAを利用できる年齢になりました。何か手助けをしてあげたいのですが、どうしたらいいでしょうか?」
これは、実際に投資信託相談プラザのIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に寄せられたご相談です。
この記事では、60代の親御さまと20代のお子さまの実例を交えながら、NISAを活用した資産承継の具体的な方法と注意点をわかりやすく解説します。
※NISAは、日本国内にお住まいの18歳以上の方であれば、どなたでも利用できる制度です。
資産運用についてお悩みの方へ

資産運用には時間が必要です。
後から焦って始めるよりも、早めに相談して「今すべきこと」を知っておきませんか?
中立的な立場のIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)が、お客様のご状況やライフプランに合わせた資産運用をご支援します。まずはお気軽にご相談ください。
▼「まずは勉強から始めたい!」という方はこちら
①延べ70,000人(※)が参加!全国各地・オンラインで開催中
→ 資産運用セミナーに参加する(無料)
※2015年12月~2025年7月末までの実績
②メールで届いてすぐ学べる!無料お役立ち資料
「NISAハンドブック」を読む
「外国債券ハンドブック」を読む
「IFAとは?」資料を読む
INDEX
なぜNISAが資産承継に適しているのか?
NISA制度は、ご両親からお子さまへの資産のバトンタッチを円滑に行い、長期にわたる資産形成を力強く後押しするための優れた手段です。主な理由は以下の2点です。
- 非課税メリット
- NISA口座で得られた運用益、配当金や分配金は、非課税で受け取ることができます。
- 長期的に運用すればするほど、この非課税効果は大きくなり、複利の力を存分に活かすことができます。
- 非課税保有期間の無期限化
- 2023年までのNISAと異なり、2024年からのNISAは非課税保有期間が無期限です。
- これにより、時間を味方につけ、子どものライフプランに合わせた柔軟な資産形成が可能となります。
NISAを使った贈与の進め方:4つのステップ
ここからは、簡単な質問形式でフローを追っていきましょう。
ステップ1:お子さまは成人していますか?
- いいえ(未成年)の場合
NISA口座を開設できるのは、18歳以上の日本居住者です。残念ながら、未成年のお子さまはNISA口座を開設できません。 - はい(成人)の場合
お子さまはNISA口座を開設できます。次のステップに進みましょう。
あわせて読みたい
ステップ2:贈与制度をどのように活用しますか?
親御さまがお子さまに投資資金を贈与する際、主に2つの制度があります。
- 暦年課税制度
- 一般的に活用される方法です。年間110万円までなら、原則として贈与税がかからず、申告も不要です。この非課税枠を活用し、NISAの投資資金をお子さまに援助できます。
- ただし、令和5年度税制改正により、「生前贈与加算」の対象期間が3年から7年に延長されました。亡くなる前の7年間の贈与は、相続財産に加算される可能性があるため注意が必要です。
- 相続時精算課税制度
- 令和5年度税制改正により、この制度が大幅に使いやすくなりました。これまでは年間110万円の非課税枠が使えませんでしたが、新ルールではこの制度を選んでも年間110万円までの贈与は非課税となり、申告も不要です。
- また、将来の相続税を計算する際も、この110万円までの贈与は相続財産に含めなくてよくなりました。
参考:国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和6年1月1日施行)
ステップ3:どのNISA投資枠を使いますか?
NISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠があります。2つの枠は併用が可能です。
- つみたて投資枠(年間120万円まで)
- 金融庁が「長期・積立・分散」に適しているとした、特定の投資信託のみが対象です。
- 成長投資枠(年間240万円まで)
- 上場株式やETF、REIT、投資信託など、より幅広い商品に投資できます。
- どちらも使う(年間360万円まで)
- 2つの投資枠は併用可能です。
- 例えば、つみたて投資枠で投資信託を積み立てながら、成長投資枠で株式を購入するといった組み合わせもできます。
ステップ4:資金はどのように準備しますか?
- 親が全額贈与
- 贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超えないで、親御さまがNISAの投資資金をすべて贈与する方法です。
- お子さまの自己資金は必要ありません。
- 親が一部贈与+子どもも自己資金を負担
- この方法は、お子さまが投資に「自分ごと」として向き合うきっかけになります。
例えば、親御さまが100万円を贈与し、お子さまが残りの20万円を自分で用意することで、つみたて投資枠の年間上限(120万円)をフル活用できます。この場合、お子さまは毎月約1万6千円をご自身で積み立てることになります。
この投資を続けることで生涯で合計1,800万円まで利用可能である、NISAの非課税保有限度額(総枠)を着実に埋めていくことにもつながります。
これは、ただお金をあげるだけでなく、お子さまが将来に役立つ「お金の知識」を身につけるための、貴重な学びの機会となります。
贈与の落とし穴:「定期贈与」とみなされないための3つの対策
ここでひとつ、とても大切な注意点があります。それは、毎年同じ金額を贈り続けると、税務上「定期贈与」とみなされてしまう可能性があることです。
「定期贈与」とは、たとえば「毎年100万円ずつ、5年間で合計500万円をあげる」というように、最初から計画された贈与だと判断されることです。
もしこのように判断されてしまうと、その年の贈与ではなく、合計の500万円に対して贈与税がかかってしまうことがあります。
このリスクを避けるためには、以下のポイントを意識しましょう。
対策1:毎年、贈与する金額を変える
例年100万円を贈与していたとしても、ある年は90万円、別の年は50万円にするなど、金額を調整することで、「今年の贈与は、今年だけの特別な意思に基づくもの」であることを明確にしやすくなります。
対策2:贈与のたびに贈与契約書を作成する
面倒に感じるかもしれませんが、書面として「いつ、いくらを、誰から誰に贈与したか」を記録しておくことは、税務調査があった際に、その年の贈与が独立したものであることを示す証拠になります。
対策3:贈与された資金はすぐにNISA口座で運用する
資金が長期間、お子さまの銀行口座に滞留していると、単なる名義貸しとみなされるリスクもゼロではありません。受け取った資金は速やかにNISA口座で運用を始めることが望ましいです。
⚠注意:税務に関する判断は必ず専門家へ⚠
ここで紹介した手法は、ご家族の状況や税制改正によって有効性が異なります。税務に関するご相談は、必ず税理士へご相談ください。
弊社へのご相談はこちら(相続に強い専門家が担当/提携する税理士法人のご紹介も可能)
→相続ご相談予約フォーム
あわせて読みたい
お子さまの成長を見守る:投資経験という「宝物」
お子さまのNISA投資をサポートする上で、特に大切なのは、「投資判断はお子さま自身に委ねる」ことです。
投資経験が少ない親御さまだからこそ、ご自身がわからないぶん、「本当に大丈夫なの?」「失敗したらどうしよう」と不安になり、お子さまの投資に口を出したくなるかもしれません。
また、投資経験が豊富な親御さまは、「こうした方がいい」「あれはダメだ」と口を出したくなるかもしれません。
しかし、親が選んだ商品で資産が増えたとしても、それはお子さま自身の力にはなりません。お子さまが自分で考え、悩み、そして選ぶこと。このプロセスこそが、将来に役立つ「お金の知識」という何にも代えがたい財産になるのです。
IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)への相談を、親子で一緒に受けるのもおすすめです。客観的なアドバイスを聞きながら、お子さま自身が納得して投資判断できるようサポートしてあげましょう。
【実例紹介】長期投資がもたらす可能性のある、未来の資産とは
ここからは、実際に投資信託相談プラザのIFAがご提案した実例をもとに、NISAを活用した資産承継の可能性について見ていきましょう。
相談者様のプロフィール
- 60代男性
- 定年退職を迎えて退職金を受取
- 自身の老後資金は確保できている
- 23歳と20歳のお子さまに資産形成の勉強を兼ねてNISAを始めさせたい
実際の取り組みとポートフォリオ
まず、親御さまは相談された年度に、お子さま2人それぞれに110万円を贈与されました。
お子さまは自己資金を足し、合計120万円をつみたて投資枠への投資資金として活用することにしました。
実際に組んだポートフォリオは、目標とする年率3.6%のリターンを目指したもので、以下の構成となっています。
- 米国株式を投資対象としたインデックスファンド 月1万円
- 日本国内の公社債を投資対象とした株式投資信託 月6万円
- 海外5資産バランスファンド 月3万円
合計月10万円積立を行う
15年間投資した場合のシミュレーション
もしお子さまが、親御さまからの援助とご自身の資金を合わせて年間120万円を毎年投資し、それが年率3.6%で運用しながら15年間継続できた場合、将来の運用資産額は約2,371万円になると試算できます。(※)
いかがでしょうか。15年でこれだけの資産を築くことができる可能性があります。これが「長期・積立・分散投資」の力です。若い世代ほど、この時間の力が大きな武器となるのです。
※この計算結果はあくまで記載した前提条件でシミュレーションした結果であり、将来の運用成果を保証するものではありません。実際の運用成績は市場の状況によって変動します。また、税金や手数料等は考慮しておりません。
まとめ:NISAから始める、未来への第一歩
お子さまへのNISAを通じた資産サポートは、単なる資金援助にとどまりません。
それは、お子さまに「お金を育てる力」をプレゼントし、ご家族全体の資産承継を考える貴重なきっかけとなります。NISAという制度をきっかけに、お子さまと将来のお金について話し合う機会を持つことで、お子さまは資産運用への関心を深め、自立した資産形成を始めることができます。
また、ご自身の資産運用や将来の相続について見つめ直す良い機会にもなるでしょう。
「相続はまだ先のこと」と考えがちですが、生前の準備が何より大切です。NISAを活用した資産承継は、ご自身の想いを次世代にしっかりとつなぐ、有効な手段の一つです。お子さまのNISAをサポートする過程で、ご家族の資産全体を見据えた相談をすることで、万一の際に慌てることなく、将来に備えることができるでしょう。
最後に、ここまでの内容を振り返り、NISAを活用した資産承継において失敗しないためのポイントを3つお伝えします。
- 年間110万円の非課税枠をうまく活用する
- 「定期贈与」とみなされないよう毎年金額を変えるなどの工夫をする
- 投資判断はお子さま自身に任せ、長期的な成長を見守る
お子さまに単にお金を渡すのではなく、「お金を育てる力」を贈る。それが、NISAを活用した資産サポートです。ぜひ、お子さまと一緒に将来について語り合い、IFAに相談しながら、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
このコラムの執筆者

道谷 昌弘
株式会社Fan IFA
本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えいたしかねますので予めご了承お願いいたします。また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

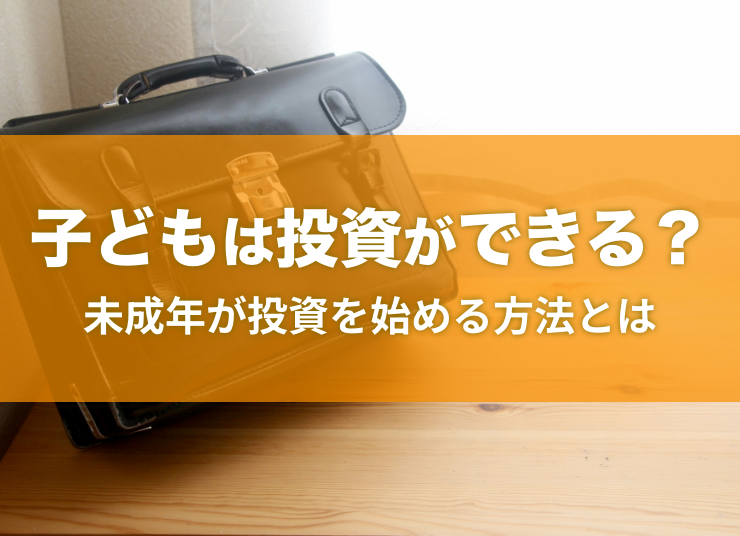
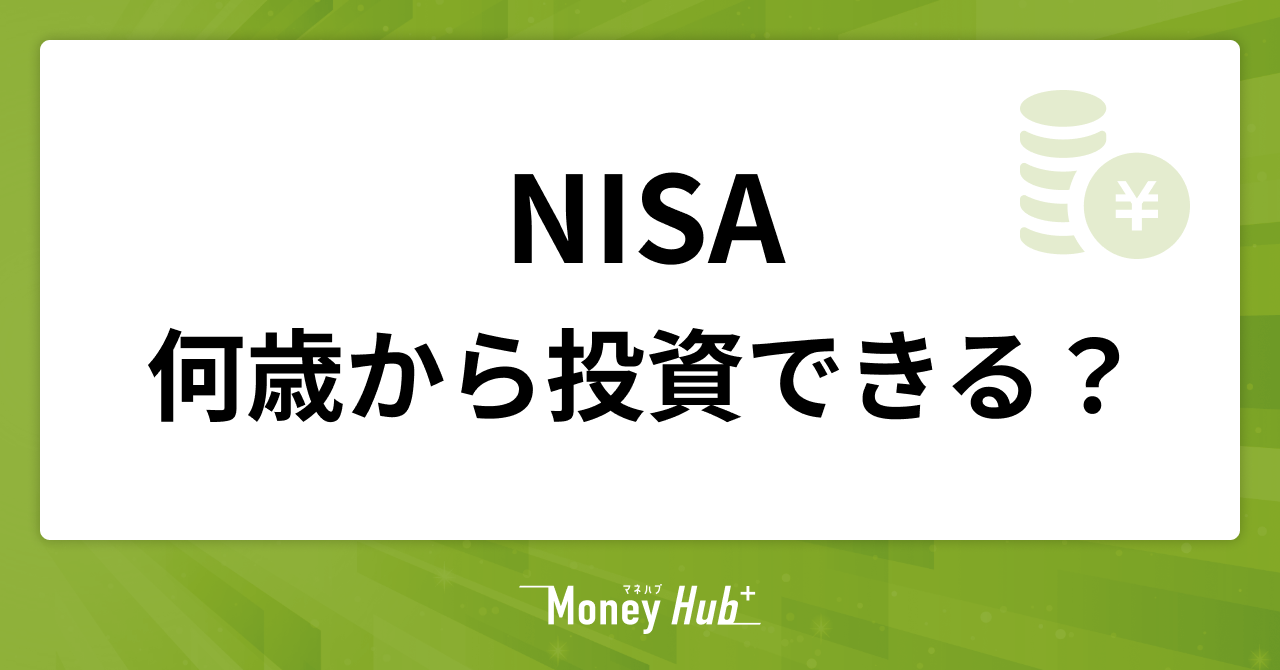
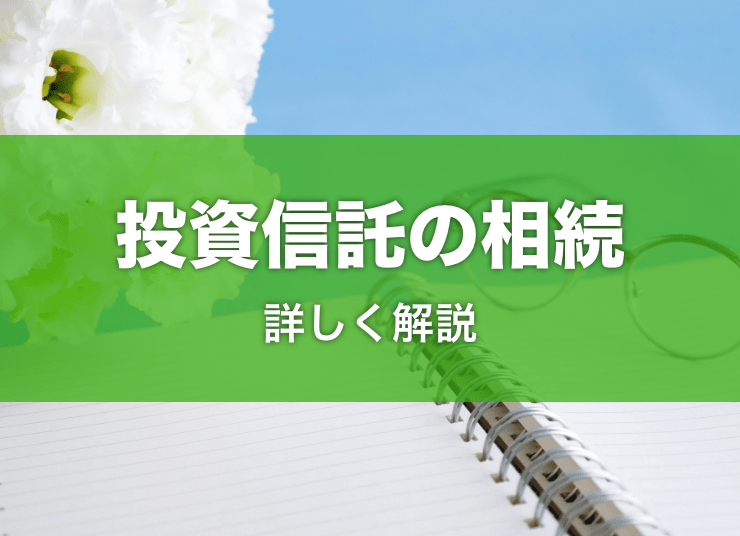
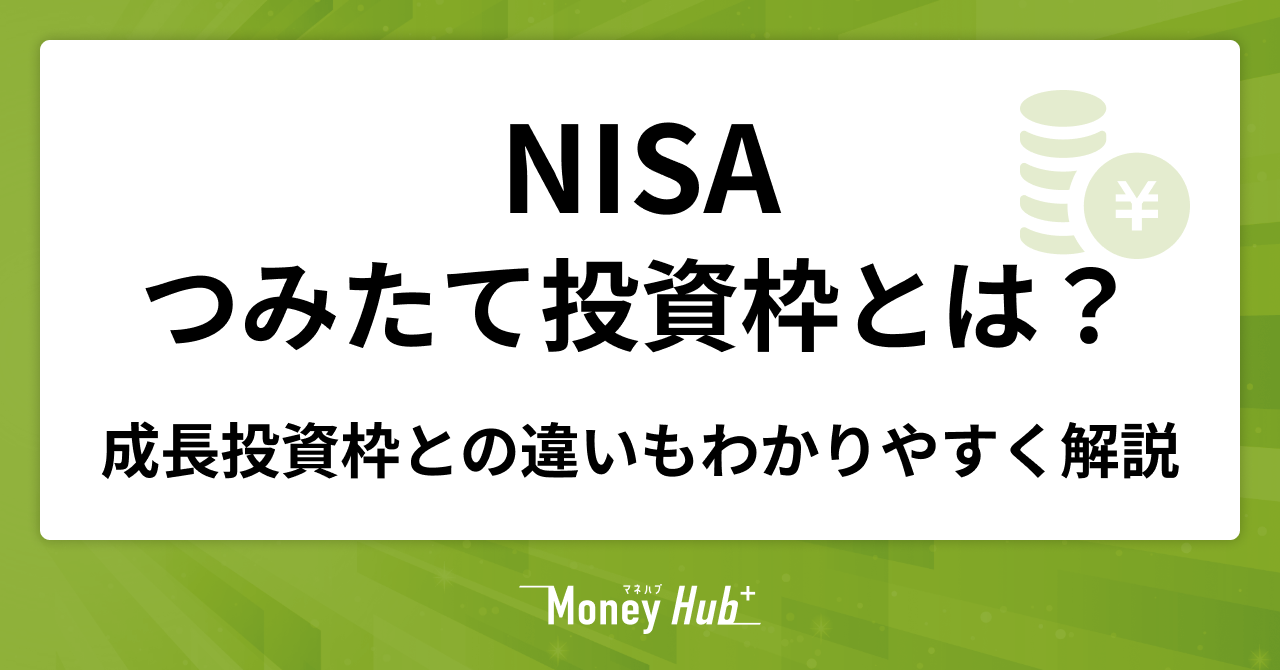
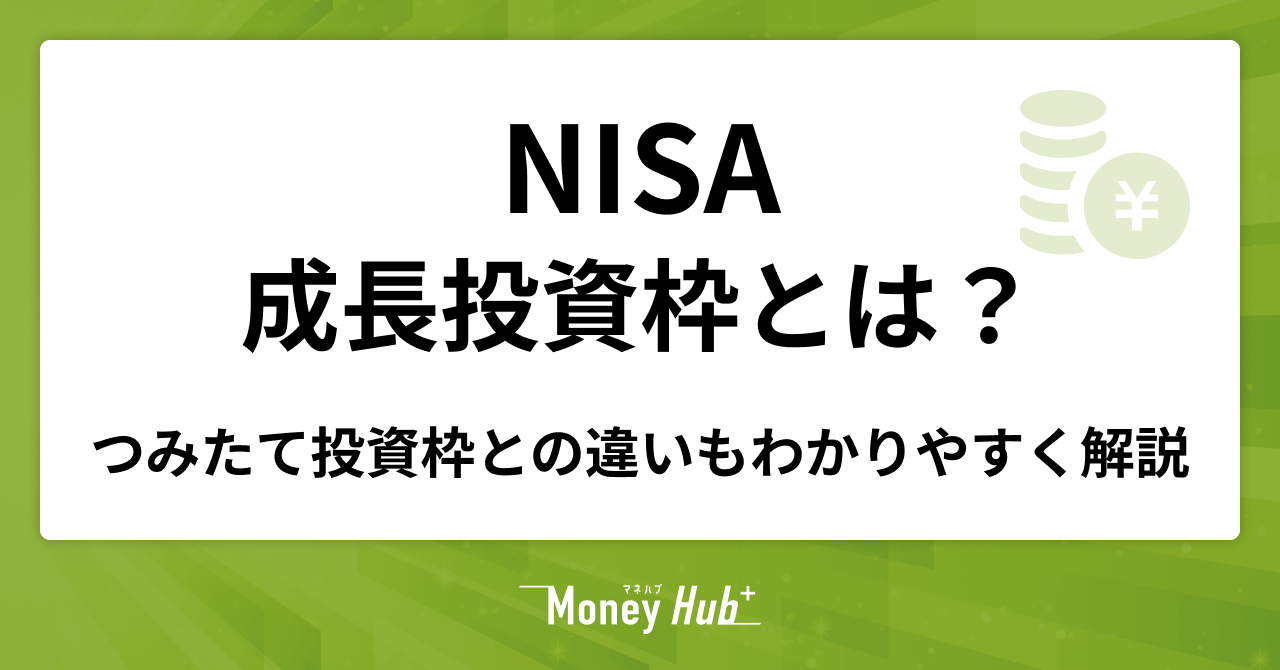































































AFP(日本FP協会認定) 大学卒業後、大手証券会社に入社。国内営業部門にて法人・個人の資産運用アドバイスを行う。8年間勤めたのち退社し、より中立的なアドバイスができるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。現在は富山を拠点に、全国各地のお客様に幅広くコンサルティングを行いながら、お客様にとって本当に良い商品提案を日々追求している。